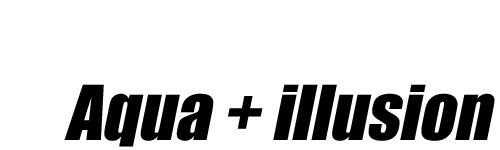
03. 栗の里のシェンリースー
清々しい風を受け、雄大なランドスケープを横目に見下ろしながら山を下った。下に降りたらあたしたちもこの風景の一部になるんだ。ちょっと感慨深い物があるね。
「う〜ん。いいなぁっ! こお言う空気!」
あたしは両腕を空に伸ばして大きく伸びをした。
「ここの空気はどこよりも澄んでる。夜空だってすごく綺麗だぜ」
「夜空……?」
今すぐにでも見たい。あたしのところじゃ霞んで見えない六等星だってたくさん見えるに違いない。空いっぱいの星。きっと、暗すぎて見えなかった星座だって見える。
「んふふ〜。早く夜になんないかな?」
「まだ、お昼にもなってないぜ?」ユメが呆れたようにあたしを見ていた。
「じゃあ、昼間の風景を楽しみながら降りてゆくしかないのだね?」
「ないのだよ。でも、俺はこの物静かな風景がとっても好きなんだよ……」
ユメは遠く、町の屋根やねを見下ろしながら言った。と言っても、家なんかまばらで、隣の家まで数百メートルの世界。畑の中には、小規模な酪農を営んでいる人もいるのか、牛舎や豚舎みたいなのが幾つか混じっていた。
「フゥリュージョンから来た連中はみんな言ってたぜ。ここはありとあらゆるものがちんけだとさ。てめぇの世界にもこんな風景、どこかにあるはずなのにな。コンクリートの石の町から食い物が出来るかってんだ」
あたしはちんけだとは思わなかった。あたしの町になかったものがここにはたくさんあった。あたしのがっこから見える都会のコンクリートの町並みより数百倍も素敵。ほとんど変わることのない風景よりも、季節ごとにドラスティックに変化する風景が好き。
「ううん。ちんけなんかじゃないよ。羨ましくなるくらい」
「羨ましい?」ユメの顔が嬉しさに満ちたようにぱっと明るくなった。「だろ? 質素だけど美しいのが俺たちの誇りなんだ」
「あたしの誇りって何なんだろう?」
「どうして、俺に聞くの。俺より、“ゆうや”ってやつの方が詳しいんじゃないのか」
そうかもしれない。でも、ゆうやはつれなくて、ここにはいない。ホントはユメがあたしのことをどう思っているのかを知りたかった。ただのお守り役なのか、それとも。
「捨てられた子猫ちゃんみたいに瞳が潤んでる。まさきって元気いっぱいお転婆娘かと思ってたら、時々、どこか遠くを見ながら泣き出しそうな目をしてる。不思議な娘」
「あたしって不思議?」キョトンとして言った。
「不思議」ユメがあたしの瞳を見て微笑んだ。「実際、色々考えてるんだなって思うよ。フゥリュージョンから来たやつは何を考えてるんだか判らないのが多かったけど、まさきは違ったな。迷ったり、決意に煌めいたり忙しいけどさ。まさきの心が向いている方向はきっと、ずっと同じだったんじゃないのかな?」
あたしはユメの顔を覗いて、しばらくの間黙っていた。
「帰りたいんだろ?」ユメが儚げに笑うと、あたしの胸はきゅんと切なくなった。
「でも。、ジュンもレンもスイも優しかったよ?」
「何、泡食ってるんだよ。何かまずいことでもあるのか?」
「ううん、ない、ないよ」あたしは思わずぶんぶんと頭を振っていた。
「遠慮しなくてもいいんだよ。帰りたければ帰れるように努力したらいい。まさきの正当な権利だぜ? ひょっとしたら、義務なのかもしれないけどね」
「そ、だね。どっちだとしても、あたしは帰るよ」
グリーンズのマルーンヒルと呼ばれる小さな街にあたしたちは着いた。ユメたちといた町よりは少し大きいみたいだけど、あたしが想像していたよりも遙かに小さかった。
「ちょうどお昼だし、そこの喫茶店で軽食か何か食ってこうぜ?」
「うん」ユメの指した方には“シェンリースー”と言う言葉と栗のいがいがと実の書かれた古い木製の看板を掲げるしゃれたお店が目に入った。
「シェンリースーってどういう意味?」好奇心に負けてあたしはユメに質問した。
「う〜ん。判りやすく言えば、深い栗色のこと。この辺、昔は栗林だったんだ」
「栗林?」振り返ってユメの横顔を見上げた。
「そ、栗林。俺がガキの頃は一大産地だったって話だぜ?」
「ふ〜ん……。栗かぁ。しばらく食べてないなぁ」
「食う? 季節はずれだけど、高〜い金を払えば食えるかもよ?」嬉々とした笑い。
「でも、あたし、お金、持ってないもん!」ちょっとだけ拗ねたい気分。
「そのことは心配するな。俺のおごりでオーケーだ」
あたしはユメに肩を押されて、そのままシェンリースーまで押し込まれた。
カラランラン。扉を開けたら、コーヒーの深い香りがあたしを包み込んだ。足を降ろすと奥ゆかしく軋む板張りの床。天井から幾つか吊された鉢植えもいい雰囲気を出してる。でも、さすがに栗の苗木の鉢植えはないようだった。ちょっと、期待したんだけど。そして、カウンターの向こうには白髪の初老の紳士が洗い物をしていた。
「マスター、こんちわ〜」さっと左手を挙げて、ユメが挨拶。
「何だ、ユメちゃんかい。今年、暑いけど、畑の様子は大丈夫なのかい?」
「ああ、去年よりトウモロコシが早く収穫できるかもしれない。や、それより、この娘に例のやつ出してやってよ。マスターのあれ、食いたいって」
「あれってあれ?」確認をとるマスターにユメはニコニコ笑顔で頷いた。「あれは季節はずれだから少々値が張りますが、よろしいですかな」こっちも何故か悪戯っぽい。
「いいよ。だって、うちのお姫さま、怒らせたら怖いから」
「何ですってぇ?」
「ホラ」気がついたらユメはカウンター席に着いていて、クスクス笑い。
「いいから、まさきも隣においで」手招きされた。
あたしはユメに誘われるままに隣にちょんと座った。その時には白髪のマスターはキッチン奥の扉を開けてあれを取りに行ったらしかった。
「あ。ちなみにまさきはここのマスターに会ったことあるはずだぜ」
「え、ないよ。初めましてだよ、初めまして」あたしは何気なく繰り返した。
「果たしてそうかな? マスターの瞳の色は何色だった?」
「……青色。え、青?」
「じゃ、丘の向こうで会ったはずのボロをまとったじじいの瞳は?」
「ちょ? ちょっと待って、何? ここのマスターとあの人は同一人物ってこと」
ユメは腹立たしいほどにニコニコと笑ってる。プチンといってしまいそうだけど、ここは堪えて努めてしおらしく。こめかみに青筋が立ちそうでも作り笑い。
「そう言うことです」
「わたしがどうかしたのかな? ユメにまさき」
「あ、い、う? あ、あたしの名前、呼んだよ? まだ、自己紹介なんてしてないよ」
あたしはオロオロとしてしまって、手のひらから汗が出るのを感じていた。
「てめぇは人の話、キチッと聞いてねぇだろ」
「き、聞いてたよ?」どうしてか判らないけど、肩身の狭い思いをしていた。
「まぁ、まぁ、二人とも抑えて」マスターは苦笑い。「まさきはこれで機嫌を直して」
と言って、マスターがカウンターにトンと置いたのは瓶詰めだった。あたしはそれを手にとって色んな角度からシゲシゲと見詰めた。
「わぉ、栗の甘露煮かぁ。甘栗も期待したんだけど。甘露煮もいいなぁ」
「少し、贅沢なんだよ。まさき」ユメが憮然としてる。
「え〜? たまにはいいじゃないかよぉ」
猫なで声。ゆうやだったらデレ〜ンとしたけど、ユメはどうなのかな。
「まさきにとってのたまには俺にとっての毎日なんだね」
効き目なし。というか、逆効果だったみたい。
「うぐ〜。ユメェ」ちょっぴり上目遣い。
「それとマスター? 昼めし〜頼むわ。いつものやつでいいから二セット」
あたしを無視して、注文するとはいい度胸だ。あとで覚えてろ。って強気なことを言いたかったけど、ここで文句なっていったらあたしのお昼ご飯がなくなっちゃいそうだからちょっとだけ恨めしそうな眼差しをユメに送って我慢した。
「……まさき、何かごちゃごちゃ思ってるようだけど、甘露煮で我慢しとけよ」
「う? うん……」あたしの浅はかな考えなんてユメにはお見通しみたいだった。
それから、マスターが持ってきた自慢のお昼ご飯は、キュウリとハム、レタスと真っ赤なトマトのサンドイッチ。プラス紅茶。きっと、どれもこれもマルーンヒルで採れた物なんだね。スーパーで売ってるどこが産地なのか判らない野菜とは違う。ここで育まれた。このパンにはマルーンヒルが詰まってる。
「……まさきぃ。じぃ〜っとサンドイッチを見詰めてるけど、楽しい?」
「楽しくはないけど……ちょっと、嬉しいかも」
長い髪をフワリとさせて百万ドルの微笑だぞ。でも、ユメはあまり興味なさそう。
と、カラララランとドアの呼び鈴が鳴った。誰かがダンと足を降ろすと床がギシギシと悲鳴を上げてる。筋骨隆々のたくましい男の人か、体重制限をオーバーしてる太めの人。
「ヨォ、マスター。ユメが可愛い女の子連れて来てるって話聞いたぜ? いる?」
野太い声。あたしが聞いた中で一番がさつで低い声だった。
「カウンター、目の前にいるだろう」マスターが素っ気なく言った。
「何だ、ノスか……」ユメは振り返って、カウンターに肘をついて物憂げに言った。見た感じではユメはそのノスって言う男が好きじゃないようだった。
「何だとは随分だな? ユメ」
「それでも俺の中じゃあ、破格の扱いだぜ」ブスッとして、明後日の方向を見てる。
「えらく、嫌われたもんだね」ノスは悪びれたわけでもなく、頭をボリボリ。
「で、用事は何? ないなら、とっとといなくなれ。目障りだ」
「お〜お、忠告しにきた友人を邪険にすると、ろくなことねぇぞ」
「……てめぇの考えなんて判ってるんだよ。帰りな」頬杖をついて気だるそうな視線。
「だったら話は早い。その娘連れて田舎に引っ込んでな。そうしたら、あの連中とやり合うことはなくなる。グリーンズは平和なものだろ?」
「帰れよ、ノス。俺はアクアリュージョンの望みを叶えるまでやめるつもりはねぇ」
「じゃあよ、そのアクアリュージョンとやらが何を望んでたっていいさ。けどよ、いつまでこんな実りのない遊技を続ける気なんだ? 心の荒んだやつが来るとな、治安が悪くなるんだよ」
「……よせよ。まさきはそんなんじゃない」静かな口調に怒りがこもっていた。
「証明できるってのか?」
「じゃあ、てめぇはどうなんだよ。てめぇこそ荒んでるんじゃねぇのか。まさきと俺を諦めさせてその“あの連中”からおこぼれに預かりたいんだろ」
「ぐ、ふ、二つの世界が一つにならなきゃならん訳がどこにあるんよ?」
相当動揺しているようだけど、かなりしつこい。
「ないだろ、別に」軽くさらりとユメが言った。「でも、アクアとフゥの恋路を邪魔するってのも野暮天かなと思ってね。……お前は生き別れた恋人を放っておけるのかい?」
「そりゃあ、どんな手を使っても捜し出そうかと……」目を白黒。
「つまり、そう言うことだ。部外者はすっこんでろ」
「へぇへ、俺は別にいいけどさ。アクアの試みを嫌う、あれ、何だかって旅団みたいの」
「ベリルな」一切の感情を律したような凍った声色だった。
「そうそう、ま、せいぜい気をつけろや」
ノスの眼が不気味に輝いて見えたのは気のせいだったのかな。とっても意味深で、言葉とは裏腹にどう考えたってあの目はユメを敵視している。
「気をつけるのは……てめぇだろ」ボソッとユメが呟いていた。
「けっ! かわいくね〜ぞ、ユメ」
「お生憎様、俺はかわいさを売って生きてるんじゃないんでね」
ユメのピリピリとした空気が隣に座ったあたしにも感じられた。そして、ノスがシェンリースーから出ていくと一転してユメの空気は和らいでいつもの調子に戻っていた。
「ユメ……。あの人は何なの?」
「――裏切り者……さ」
それっきりユメは喋らなくなって、いつかと同じようにあたしはユメに問えなかった。あたしがここに来る前、ユメとみんなのこの世界で何があったの? 教えて欲しい。
シェンリースーでお昼を済ませたあたしたちは考古学者さんの住んでいるうちに向かった。その人は考古学以外にも様々なことにも詳しいらしくて、マルーンヒルとか、グリーンズ、ボーダーランドの辺りでは通称“賢者”さんと呼ばれているらしかった。
確かに、ドアをくぐれば本の山。だけど、博識の証かと言われればどうなんだろう。
「ヨウさん、いる?」
「いるよ〜。いるけど、ドアを開けたショックで本の山が雪崩れて、埋まったぁ〜」
「埋まったぁ〜あ」
変な声を上げて、玄関先から続く本の積雪をかき分けてユメが行く。廊下を越えて、居間に行って、でも、ここは書斎なのかな? その奥のドアを開けようとしたら今度は開かない。引いても押しても蹴っても、どうにもならなくてユメは剣を鞘から引き抜いた。
「俺、昼間っから何やってるんだろ?」
大きなため息をついてがっくり肩を落としてる。と、言いつつもユメは結構冷静で、ドアの蝶番の留め金を柄でゴンゴン叩いて外していた。
「ねぇ、ユメ? ドアをまっぷたつに斬ったりしないの?」漫画のように。
「硬くて斬れねぇよ。それに刃こぼれしたら、肝心なときに困る」
「そうなんだぁ〜」
感心している間に、ユメは扉を外してヨウを捜していた。
「お、いたいた、ヨウ? 雪山でもないのに遭難だなんてやめてくれよな」
手を差し伸べて、崩れた本の山に埋もれたヨウを助け起こした。
「いいだろ? とってもスリリングで」
「スリルの使い場所を間違ってるんだよ」
「まあ、細かいことは言わずに……」
ヨウがあたしに気がついた。ユメの顔を見ていた目がくるっとあたしを見た。
「五百十二人目の挑戦者ですね」そして、いきなりヨウが言った。
「ジュンにはそう聞いたけれど……」自信なく瞳を伏せてあたしは言った。
「ええ。マスターが女の子だって言ってましたから、そうでしょう」
「そ、そんなんでいいの?」
「いいのじゃないでしょうか? 違う人に話したからと言って問題はありませんし」
「はぁ……」
賢者だと言うからどんな生真面目なおじさんなんだろうと思っていたけど、全然違っていた。ただの学者肌の変なお兄さんみたいな感じがした。
「ともかく、ダイニングへ行きませんか? ここじゃ落ち着きませんから、向こうで紅茶か何か、冷たいもので飲みながら……」
ヨウは慣れたものなのかホント雑誌の山を器用によけて歩いていく。ユメとあたしは本の角を踏んだり、つまずいたり大変だったのに、ヨウはスイスイ歩くんだから。
「ヨウ? たまにゃぁお片づけしろよな。歩きづらくてかなわないぞ」
「わたしは特に……」キョトンとした風にヨウは言った。
「てめぇはいいだろうけどよ。客はどうするんだ? 客は」
「お客はお客です。散らかった家を見てどう思われても構いませんよ。瞬く間の客人よりわたしは自分の生活の方が大切ですので……」
ユメは黙っちゃった。でも、ダイニングに連れられていくと別世界だった。あたしは居室と同様に散らかり放題だと思っていたのに意外だった。食器類は食器棚にきちんと並べられて、水回りも清潔そのもの。流し台には水垢の一つもついていなかった。当たり前のことなんだけど、意外に思えた。
「ねぇ、これ、ヨウが片づけてるの? 誰か、他に女の人いない?」
「わたしだけですが……どうかしました?」
部屋はあれだけ散らかってるのに、ここだけ整頓されているなんておかしな気持ち。納得できないような、釈然としないような。でも、キッチンで流れるように手際よく紅茶を入れている姿を見ていると、ここだけ片づいているのも判るような気がする。
「さてと……お話の続きを……」
トレイにティーカップ三つと砂糖、ミルクを乗っけてヨウはあたしたちを促した。
「座って? リラックス」あたしの学者さんのイメージとは似ても似付かない。
あたしとユメは顔を見合わせて大人しく席に着いた。
「なぁ、ヨウ」ユメはドスンと椅子がひっくり返りそうな勢いで座った。
「何ですか?」穏やかな笑顔。
「いつも、話長いから手短に頼むよ」
「はぁ……」
ヨウはまるで自覚症状なしのようだった。だから、逆にユメが困ってた。
「いいや、ちゃっちゃと済ませちゃって」
居心地が悪くなったのか、足を組んで紅茶をがぶ飲みしてる。
「ああ! 舶来品のお茶なですからね。もっと味わっていただかないと。高いんだから」
「高いって言ってものど渇くんだから仕方がないだろう?」
すると、キッと鋭い視線でヨウがユメを睨んだ。そしたら、ユメはもうぐうの音も出ないみたいで、言葉もなく黙ってる。あたしはそんなユメの様子を面白がってみていたら、恨めしげにユメがあたしを見詰めてた。
「……ユメのことは放っておいてもいいでしょう。さてと、どこから始めましょうか……。え〜と」
「まさき」あたしは察して答えた。
「まさきちゃん?」
「判んないことが多すぎて、どっから聞いていいのか判らない」
それはホントのこと、あたしは何も判らないからヨウに聞きに来た。
「……では、核心から」ヨウは意外と直球勝負の性格なのかもとあたしは思った。「フゥリュージョン、俗に『とわの瞳』と呼ばれる秘宝の片割れを探すこと」
「それは何となく判ってた。じゃあ、その場所」
「大断絶――マルーンヒルを越えたずっと南のどこか……」
「それだけ?」あたしは既にちょっぴり残念の領域に片足を突っ込んでいた。
「それだけですね。ファーストチャレンジもたったの五年前ですし、資料もなかなか集まらなくて――」
「言い訳は要らな〜い!」あたしはヨウににじり寄った。
「ただ」目が上を見てあたしの追及を避けてる。
「ただ――?」
「まさきと僕たちの世界は一つだったと言います。そして、まさきが帰るための条件、憶測の域をほとんど出ていないのですけどね」
ヨウの瞳の奥底が煌めいたように思えた。憶測だとは言っていてもそれなりに答えに自信があるようだった。あたしはヨウの瞳を見詰めて息を呑む。
「フゥリュージョンを見つけだし、何らかの方法で二つの世界を一つにすること」
「……で?」あたしは思いっきり投げやりにつっこみを入れていた。「その『何らかの方法』って何なの?」そこが判らなかったらヨウの家にきた意味がない。
「判りません」
言うだろうと思った。レンに『賢者に聞けば全部判る』って言われて期待していたけれど、ヨウもただの学者さんってことなんだ。それともあたしは意地悪? と、不意にあたしはどうしても聞きたいこと、聞かなくちゃならないことを思い出した。
「あの、も、一つだけ、いいかな」あたしは恐る恐る。
「いいですが――。どうしたんですか、急に静かになって」
ヨウに気を遣ったつもりだったけど、ヨウはそう感じなかったみたい。
「……みんな、どうして、こんなおかしなことを素直に受け止めているのか聞きたい」
「異常も慣れてしまえば普通になるんですよ。それにね、異邦人が旅する地域はごく限られています。……僕の言いたいこと、判りますよね?」
「ほとんど誰も知らないってこと?」
ヨウは瞳を閉じて黙って頷いた。そっか、ここはあたしには中心かもしれないけど、世界のホンの片隅なんだ。でも、逆にそれはとっても怖いことなのかもしれなかった。まるで何かの終末思想のよう。しかも、それはひょっとしたら自分の知らないところで始まって、知る術もなく勝手に終わっているたぐいのもの。だったら、ある意味、最悪。
「ヨウ〜。頼むぜ〜?」
ユメは飽き飽きした様子で背もたれに仰け反ってる。そのままひっくり返っちゃえ。
「じゃ、じゃ、もうこれで最後!」
「……まさきの好奇心が暴走してる……」ボソッと嫌なこと言わないでよ。
「二つが一つになるとどうなるの? と、言うか待って。……これがほとんど誰にも知られていないことだったなら、誰が一つの世界が二つになったって判るの?」
「……まさきがここにいることがそれを証明しているのではありませんか?」
「でもでも、あたしが大うそついてないって言い切れる?」
ヨウは首を横に振っていた。
「しかし、まさきのような事例は既に五百十二件目です。しかも、僕たちとは明らかに異質のモノを持っている。全員が虚言癖を持ってるはずはないでしょう?」
ヨウの言葉があたしの胸にズキンと刺さった。あたしは言葉の通じるただの通りすがりなんだ。あたしは誰にも言えない淋しさを密かに感じていた。
「それはちょっと、突飛なんじゃない?」
「証拠があってもなくても、証明できてもできなくても事実は事実です」
結局、ヨウと会ってはっきりしたことはどこにあるのかもいまいちよく判らない『とわの瞳』の片割れ、フゥリュージョンを見つけないとスタート地点にも立てないこと。あたしがここにいることが全てなんだってこと。
でも、ヨウのうちを後にしてしばらくユメと黙々と歩いていると込み上げてくるもやもやがあった。ヨウは知ってることをちゃんと説明してくれたみたいだし、足りないこともあるだろうからとアクアリュージョンとフゥリュージョンのことを色々書いてある古くてちょっと黄ばんだ本を一冊くれた。けど、
「けぇっきょく、全然ダメじゃん!」あたしは憤りを感じてユメに嘆いた。「もっと、色々、たくさん教えてくれるのかと思っていたのに、勉強不足よ、勉強不足」
「そんなに怒るなよ。まさき 可愛い顔が台無しだぜ」
「そんな……ふざけないでよ。あたし、これでも真剣なんだからねっ」
「ハハ」ユメは苦笑いしてまともに相手もしてくれない。
「だって、あんなことちょっと調べたらあたしにでも判りそう」
「でも、いいだろ? 代わりに本をもらってきたんだからさ」
「本をもらったって言ったってさ、カビの生えた本なんかより生きた情報でないと」
「でも、みんなあれで納得してたぜ? 疑問を挟んだのはまさきが初めてだ」
「何であんなんで納得できるの?」何故かあたしは泣き出しそうな声色になった。
「そこから先は……更に知りたいやつにしか教えない」
「え……?」
「表面だけを見て判ったふりをするようなやつに大切なことは教えられない。そ・し・て、ヨウのくれた本、ちゃんと読めよ。それ、あいつが研究してまとめたんだぜ。だから、それはただの知識の塊や読み物じゃない。生きてる知恵だ」
そう言ったユメの表情はあたしには煌めいて見えた。
「そいつを受け取れたのは……今更、言うことないだろ」
と言うからには、もらえたのはきっとあたしだけなんだろうな。そう思うともらった本が急に愛おしく思えてギュッと抱き締めた。でも、あたしの中にいるどこかクールなあたしがそれだけじゃダメなんだと訴えていた。
「けど、いくら知ったとしてもフゥを見つけないと終わらない」ユメを見上げた。
「そう……だ」
トボトボと街の反対の丘から続く街道を和気藹々、時々、黙々と歩いていった。あの丘からここまでは多分五キロくらいあって、あそこから見るとあたしたちはごま粒よりも小さくて完全にランドスケープになってる。
不思議な気持ち。全ての行程を踏破するのは大変だろうけど、目的の見えなかった向こうでの生活と違って、大きな達成感があるような気がしていた。おうちに帰る。あんな簡単だったはずのことが今はとても難しいことに化けていた。
「なぁ、まさき」突然、何の脈絡もなくユメが言った。
「な。なぁに?」考え中の呼び声に、あたしの思考が追いつけない。
「俺、マスターに晩飯の弁当頼んだの忘れてたわ。ちょっともらってくるから、まさきは先に行ってていいよ。うん。すぐに追いつくから」
バイバイって手を振ってる。こんな幼気な女の子を一人で行かせるなんてひどい。と言うか、もうすぐ夕方なのにまだ歩いていくつもりなの? でも、仕方がないからあたしはメインストリートを南へと歩いていた。相変わらず民家はまばらで、人影も少ない。道ばたには野の花が遠慮なく咲き乱れてて、いいな。
「てめぇが、アクアの選んだチャレンジャーか?」
突然、予想さえしていない方向から声がして、あたしは心臓が止まると思うくらい驚いた。声の主は大木に寄り掛かり、腕を組んで死んだ魚のような目であたしを睨んでいた。
「だったら、何だって言うの?」つい、いつもの攻撃的な口調が出てしまう。
「威勢がいいじゃんか。少しは怖がってみるとか、ないのか?」
少し余裕が出て、あたしが見やるとご多分に漏れず剣を腰に吊っていた。
「あんたを怖がる理由なんてない。怖くたって怖くない!」
「へん。ま、いいや、そんなの。怖がって欲しいわけでもなし」髪の毛を左手でクシャッと押さえた。それから思い出したように「てめぇ、何て名なの?」
「ひ、人に名前聞くなら、さ、さ、先に名乗りなさいよね」
腰に手をもっていったから、剣を抜くのかと息が詰まったけど、違ったみたい。
「……リンネ」すっごく不本意そうに不機嫌に言ってきた。でも、わりと素直?
「ふ〜ん。って、ええ? お? 女の人?」素っ頓狂な声になっちゃった。
「……女じゃ悪いのか……」
「だって、だって。声、低いし。男の人みたいな格好してるし。言葉も悪いし」
枚挙に遑がないってこういうことを言うのかな。
「あら探しするな」仏頂面のリンネがいた。
「あら探ししたんじゃないんだけど……。あらしか見えないんだもの」
リンネは言葉を失っていた。どちらかというと、キョトンと言うよりは唖然としているようだった。
「お前って、こう、信じられない言動をするな」まじまじと見詰められちゃった。
「放って置いてよ」あたしは腕を組んで流し目で、憤慨する。
「それが出来るなら最初から構っちゃいねぇよ。だが、俺たちが欲しいものが緑柱石……ベリルである限り出来ない相談だな」取り付く島がないってこういう事を言うのかな。
「どういう意味よ?」でも、いまいち意味が判らなかった。
「……頭の書いて悪いな」
余計なお世話さんだ。言われなくても判ってるんだから。そんなことより喋らせるのにどうしようかと考え始めたら、リンネは思いの外フツーに先を続けてくれた。
「アクアマリン……アクアリュージョンは不純物を含むベリルってことさ」
「でも、フゥリュージョンは緑柱石じゃなくて、ガーネットで出来てるんでしょ?」
ゆうやの受け売り。ほとんど知ったか振りであたしは答えた。
「例えだよ。た・と・え」
「アクアマリンのアクアリュージョンから不純物を取り除く、それがベリル。アクアの望みが何だか知らないけど、俺たちにフゥは要らない」
「でも、あたしはアクアが欲しい!」
「やっぱな。そう言うと思っていたよ」一瞬、目を閉じて、カッと見開いた。
「そうでなくっちゃ、面白くないぜ。大体、骨のねぇのが多すぎるんだよ」
どういうのが骨のあるやつなのか見当はついていた。この手の人がこう言う時に欲しい相手はパワーバカに違いないんだ。
「ま」リンネは長い髪の毛をボシャボシャッとかいた。「どっちにしろ、てめぇは鉱石に色を付ける不純物なのさ。……やっちまいな」
リンネの合図に十人くらいの男たちが現れた。どうしよう。ユメがいなかったらあたしには何も出来ない。ジュンにもらったセイの剣なんてあたしにはまだただの飾り。囲まれる前なら、あたしの足で逃げ出せるかも。と思ったけれど、アーチェリーを持っている人もいるから、背中を向けて一目散に逃げるわけにも行かなかった。
「何だ、思ったより目、つけられるの早かったな」
ユメがマルーンヒルの方角からノンノと現れた。しかも、目の前にベリルの連中が十何人もいるというのに落ち着いていて、慌てる様子なんて全然ない。
「マルーンヒルのユメか。また、厄介なのが敵に回ったな」
「俺ってそんなに有名なの?」リンネの言葉が意外だったのかユメは目を丸くしてる。
「有名というのとはちょっと違うんだろうな」
「どおせ、あれだろ、シェンリースーに出入りしてるおかしな遊び人……。てめぇんとこのノスの野郎があることないこと吹いて歩いてるんだろ?」
「ノス?」考えてる。「ああ、あの役立たず。それは関係ないよ。強いものなら何でも尻尾を振るようなやつは信用できないね。あれを信用するくらいならユメを信用するぜ?」
「ありがたいけどな。気にしないでくれる?」
「それが不思議なんだ、何故だ? いつもは、中立。へっ、俺たちのやることにゃあ不干渉主義だったじゃねぇかよ? そいつ……てめぇのこれなのか?」小指を立ててる。
「どっちでもいいだろ? ただ、今度ばかりはベリルの好きにさせないだけだ」
「ハッ!」リンネは腕を組んであざ笑った。「それこそどっちだっていいさ。俺たちはアクアの思い通りにはさせない。俺たちは俺たち。向こうは向こうで勝手にやればいい」
「でも、二つは一つになるべきなんだ」あたしは思わず口を挟んだ。
「どうして?」リンネの純粋な眼差しがあたしを見ていた。
「判んない」正直な気持ちを言った。「判んない、けど、あたしは帰りたい。アクアが行けと言ったから行くんじゃない。フゥに待ってる人がいるんだ。あたしは二つを一つにしたいんじゃない。帰りたいから最後まで行きたいんだ!」
「……そんなこと言ったやつ、初めてだ」
あたしはドキンとした。と同時に、言い表せないような焦りみたいなものを感じた。
「みんなこぞって言ってたぜ。『二つを一つに』ってな」
「ユメ?」あたしは隣に立ったユメの顔を見上げた。
「そ、まさきみたいのは初めてだ」どこか懐かしげな眼差しがあたしを見ていた。「……良くも悪くもまさきのやってきたことはほとんど初めてだな」
「今までの連中とはひと味もふた味も違うって訳か? けど……」
言いかけて、リンネは腰から下げた剣を鞘から抜いた。あたしがもらったセイの剣よりも少し幅があって、太陽の光を受けて煌めいてる。綺麗。だけど、あれが、今までアクアリュージョンに来た挑戦者たちのどれだけか判らないけど、行く手を阻んだんだ。
「こいつをかいくぐって生き抜いたやつは数えるほどしかいないぜ」
自信満々とはこのことを言うんだろうってくらいリンネは生き生きしていた。
「そんじゃ、まさきにゃこここでおさらば願いますかね?」
「嫌だ!」あたしはリンネにかみつく勢いで言った。
「おおこわ」これっぽっちも怖くないくせに何を言ってるんだ。「さて……」
リンネがニヤリとほくそ笑むとベリルの連中があたしたちをぐるりと取り囲んだ。
「まさき! 剣を抜け」ユメがあたしを背に回して剣を抜いた。
「抜いたって、まさきにゃ何も出来ねぇさ。俺たちはプロだぜ?」
「まさきにここで死なれちゃ困るんだ」
「まさきは口ほどにもないが……、やっぱ、ユメがな。ま、今日は初顔合わせのつもりだったし、てめぇはファイナリストにさせない」
リンネはきつく唇を噛んでキッとあたしを睨み付けていた。どうして、そんな恨みを含んだ視線をあたしに向けるの。あたしは何もしていない。少なくとも、まだ。
「ファイナリストはりんいちで最後だ。そして、チャレンジャーはまさきで終わりだ」
「違う! 何もかもあたしで最後だ。帰るために二つを一つにと言うのならそうするし、リンネを殺せと言うのなら、あたしはそうするしかない。何がどうでもあたしは絶対に帰るんだから」
「気の強い娘だね。命乞いはしなくてもいいのかい?」
「す、するもんか!」負けそうだ。こんなシチュエーションなんか初めてで、喋ってないと泣いてしまいそうだった。命の掛かった駆け引きなんてやったこともない。
「へん。いつまで続くかな?」リンネがあごをしゃくったのが見えた。「やっちゃいな」
『やっちゃいな』リンネの言葉と勝ち誇った笑みだけがやけに印象に残っていた。それから、あたしは緊張のあまりのなのか都合良く気を失ったようだった。ユメの剣を持った大きな凛々しい背中があたしの見た最後のヴィジョン。
「……お〜い、まさき。いいかげん、起きろよ」
ぺちぺちと頬を打つのは誰? 朝にはまだ早いんだからね……。
「お〜い……。ねぼ助、めし〜食っちゃうぞ〜」
「ダメよ、ダメ! あたしの分残しておいてヨ? おかあさん」
「なぁに寝ぼけたことを言ってるんだ?」呆れたような男の人の声。
「あ・れ?」あたしの目の前にしゃがんでいたのはユメだった。
「あれじゃないだろう、あれじゃあ。ホラ、行くぞ、まさき」
ユメが手を差し伸べてあたしはその手を掴んで立ち上がる。あれ? あたしは眠っちゃったのかな。大きな木陰の下でユメを見上げて。でも、ここはボーダーランドの丘じゃない。違う。いくら何でも朝がこんなに早く夕暮れになるはずがない。そして、
「ユメ! ベ? ベリルは?」
「追い返した」ユメはあたしの目を見てくれなかった。「リンネがひっくり返った相手を襲うのはフェアじゃないってね、引き下がってくれたという方が正解」
「じゃあ……二度目はないってことなんだね」
「多分ね。ま、運がよかったというか、何というか、リンネの気まぐれで命拾いだ」
「やっぱ、これ、使えなきゃダメなんだね……」
あたしはセイの剣の束をそっと握った。手が震える。だって、これでもうあたしが帰ると言うことは誰かの命と引き替えになるって決まったようなもの。ベリルが邪魔してくる限り、あたしはきっと誰かを殺す。でなければ、あたしが死ぬ。
「怖い。あたしホントに帰れるのかな?」
あたしの問いかけにユメは答えてくれなかった。その代わりに瞳をじっと見詰めて、ユメの瞳が帰れる帰れないはあたし次第だと語りかけているようにも見えていた。
「――あたしはこの剣をどう使ったらいいの……」
結局、それしかないんだね。いつまでユメがいてくれるのか判らないから、自分の身は自分で守れるくらいにはならないと。
「軽快なフットワークを活かせる戦い方……だな」ユメが答えてくれた。
「軽快な?」
「あとな、それ、斬りつけるんじゃなくて、突き刺すための剣だ。レイピアってやつでね、セイもそうだったんだけど、腕力そんなにはないだろ? まさき」
「うん……多分」
「だから、まさき……間合いに入り込んだら、ためらわずにそいつを心臓に突き立てろ」
ユメの視線が怖かった。本気にユメはあたしのことを考えてくれている。ユメの痛い眼差しはあたしに、『帰りたいなら生きろ、生きたいなら戦え』と訴えていた。
「まさきは……体重が軽そうだからなぁ。盾を持たせたいけど……機動力が出せないんじゃ魅力半減だし……。どうせ、野郎の段平や大剣なんか止められねぇだろうし」
「でも、あたしだってユメの背中を守れるようになりたい!」
「じゃあまずへっぴり腰、あんど、及び腰をなんとかしてくれ」
「でも、一日じゃ絶対無理だよ」
「判ってるって。そんな無茶は言わないさ」
でも、あたしはアクアリュージョンにいる間にユメの背中を守れるようになれるとは思っていなかった。フゥリュージョンを見つけるのにどれだけかかるのか判らないけど、一月二月、ううん、一年やそこらユメに教わったくらいじゃ足りないような気がしていた。
「あ〜あ、すっかり暗くなっちまったし、今晩はマスターんちに世話になるか」
フと夜空を見上げてあたしは驚いた。あたしのいたところとおんなじ。ジュンの家にいたときには気がつかなかったのに。さそり座や乙女座が見えた。つまりは、黄道十二宮、全部同じ。と言うことは、全天があたしのフゥリュージョンと一緒と言うことなんだね。
「夜空を見上げてどうした、まさき」
「何でもないよっ! ただ、星空が綺麗だなと思って」
「そっか、……まさきって霞んだ空しか知らないんだっけ」
「うん……こんなに澄んでてはっきりくっきり星が見えるのなんてあんまりない」
「じゃあ、その双眸にしっかりと焼き付けて行けよ」
「うん……」
まともなベッドでゆっくりと休めたのはこの夜が最後だった。星の降る夜空の下でのキャンプはロマンチックだなと思っていたけど、幾晩も続くとただの苦痛になった。そう、シェンリースーのマスターの言葉、よく覚えてる。
「始まれば終わるし。終わらなきゃ次が始まらない。どう終わらせるかはその人次第だけれど、まさきならこの物語、どう終わらせたい?」
答えはまだ見えなかった。