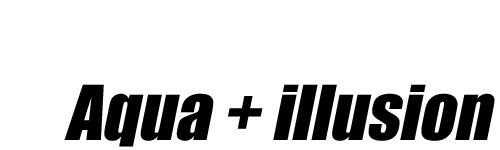
04. シャンルーの架け橋
朝早く、今度こそシェンリースーを後にして南に下る。くねくねした街道とその脇には水田。そして、幾つかのイチゴ畑が目に入った。
「ね、ね、ユメ」あたしは嬉々としてユメの袖を引っ張った。
「イチゴ狩りは……ゼッタイにダメだ!」
言う前に釘を刺された。何だかよく判らないけど、とっても悔しい。
「大体、お前はなぁ、緊張感がなさすぎるんだよ。観光かなんかと勘違いしてない?」
「ううん、してない」にっこり微笑んで、会心の笑みのつもり。
「何だかなぁ。昨日、ベリルに襲われたときには相当へこんでたのに」
「あたし、こう見えても打たれ強いから」と言うか、あんなこと忘れたかった。
これから先にずっとこんなことがあるんだったら、今だけでも記憶の外に置いておきたいことだった。先送りにしても何の解決にならないことは判っていたんだけどね。
「ふ〜ん?」ユメは見透かしたような意味深な笑いを浮かべていた。
それから、無言でひたすら歩くことお昼まで。こんなに半ば無目的に歩いたのは、高一の時にあった研修旅行の謎企画、二十キロハイキング以来のような気がしてた。そして、ユメと来たこの場所はあたしの中で一番印象に残っていた。
「まさき。あれが……大断絶。グリーンズとノーシーランドを分かつ谷……」
ユメの指した方向に、見たこともないような大きな切れ目が見えていた。アメリカ、グランドキャニオンや北海道、層雲峡のような渓谷じゃなくて、一つの大きな亀裂がどこまでも走っている。対岸までの距離はどのくらいなんだろう。
「ユメ、向こうまでの距離……」
「ニキロとも三キロとも。正確な距離は誰も知らないよ。測ったやつなんかいない」
「そ〜なんだ」と、あたしは独り言のように呟いて、崖っぷちまで行ってみた。
「あ〜、まさき。あまりはじっこに行くなよ。崩れやすいから」
あたしはユメの言葉を聞き流して、じっと景色を眺めていた。大断絶とまで呼ばれる大地の亀裂。遥かな向こうに瀑布があるのを見て取れた。と言うことは、この底には川が流れているのかもしれない。確認しようにも、ここから身を乗り出すのはちょっと怖かった。落っこちたら、絶対にさようならだ。
「どうやって、向こうまで渡るの?」
「それを考えるのがまさきの仕事だ」
少しくらい、ヒントをくれたっていいんじゃないの。けち。でも、声には出さない。
「じゃあさ、空を飛べる乗り物ってないの?」両手を広げてパタパタとして見せた。
ロープなんて張ってなかったし、あたしにロッククライミングなんか出来るはずもなかった。落ちるのは簡単だけど、登ってこれなかったらどうにもならないし。
「生き物ならいるよな」
指を差された方角を見上げたら確かにいた。けれど、プテラノドン? 図鑑でしか見たことはないけれど、それとは何となく違うような気がした。しばらく、目を凝らして見ていると、飛竜に見えなくもない。どっちにしても、大断絶を越えるにはあれに乗るしかないらしい。
「でも、あれ、気難し屋だから。どうだろう? まさき、交渉は得意かい?」
「交渉って、あれは喋れるの?」もう、何を言われたって驚かないんだ。
「う〜ん、喋るって言うかなんというか。どっちかというと、テレパスかなぁ?」
形容に困った様子で、うんうんうなりながらユメが言った。
「テレパス?」あたしは訝しげにユメに問うたのに違いない。
「そ、頭の中に直接、話しかけてくる感じがするんだ。しかも、気に入ったやつにしか話しかけてくれないんだよ。でも、ま、まさきは……彼ら好みぃなのかなぁ」
ユメは腕を組んで、あたしを見ながらニヤリとした。
「は、会って話してみなけりゃ判んないじゃん」
「そりゃそうだけど……あ、おい、ちょっと待てよ。何でこう行動だけは早いんだ?」
あたしは渋るユメを放っといてズンズンとその“飛竜”みたいなのに近寄っていった。先に進まなきゃ始まらないんだから、アタックあるのみ。
「ねぇ」あたしは言った。
「……」そいつはあたしに一瞥をくれるとまたあっちを向いてしまった。
「ねぇって言ってるでしょ!」あたしはそいつの足を思いっきり蹴っ飛ばした。そしたら、ようやくあたしに向き直って怒鳴り散らしてくれた。
「てめぇは何してくれんだ! 初対面に向かって蹴り入れるたぁどういう了見だ!」
「あんたが無視するからでしょう?」腕を組んで鋭い目つきを送ってみせる。
「無視したんじゃねぇ。放っておいたんだ」
「どっちだって同じでしょ。この分からず屋が」
「てめぇは誰を掴まえてものを言ってんだ? プディングより柔らかい俺さまのノーみそだぞ」
「ふ〜ん、じゃあ、つるつるなんだねっ!」負けないぞ。
「つるつる?」動揺して上擦ったように聞こえる。そして、ちょっとだけあたしは勝ち誇る。「つまり、てめぇは俺がバカだって言いてぇんだな?」
「だってそうでしょ? こ〜んな可愛い娘が乗せてって言ってるのに無視するなんて」
「……自分で言ってりゃ世話ないよな」あたしの背後でユメの呟きが聞こえた。
「何か言った? ユメ」
「気ぃの強い娘だねぇ」ため息まじり。
「こっちはこっちで、なぁ〜んか言いました?」あたしは勢いよく振り向いた。
「いんや、何も」目を悪戯っぽくクリクリと閃かしてそいつは言った。「……けど、てめぇと一緒に断絶を渡った向こうを冒険してみるのも面白そうだな」
「え?」意外な言葉にあたしは言葉に詰まった。
「一緒に行ってやってもいいって言ったんだけど。やっぱりやめる?」
「やめない」反射的にあたしは言った。「えへへ、案外、優しいんだね」
「いいや、全然」高い目線で、澄まして言われると何だかカチンと来る。
「ただ、てめぇと行ったらさ、何か面白いものが見られそうな気がしてね。――で、さ。それとは別に報酬に何くれるんだ? ただは嫌だぞ、ただは」
報酬をよこせと言われても、あたしに渡せるものは何もなかった。あるのは千円札と小銭じゃらじゃらの財布と、つまんない教科書が数冊。セーラー服。飛竜が喜びそうなものが何かは判らないけど、どれも喜ばなさそう。あたしは困った顔をしてユメを見た。
「俺の畑で採れた玉ねぎ一月分やるよ」
「何で生で食えないものを言ってくるんだよ。それに泣けるものは嫌い」
「じゃあ……」ユメは腕を組んだ。「あとはせいぜいリンゴか? 小麦はいらねぇだろ」
「ロクなもんねぇな」不平不満いっぱいにそいつは言った。「でも、ま、この前のやつより百倍ましだし。いっか。いいよ。リンゴ、ただし、蜜がたくさんなのよろしくねっ」
拍子抜けしてしまいそうなくらいに可愛らしかった。
「あんたってさあ、いけ好かないアホなのか、可愛らし〜飛竜さんなのか、どっち?」
「どっちでも」でっかい目玉を閃かして、悪戯っぽい煌めきが瞳の中に見えた。
そんな様子を見ていたらきっと両方なんだろうなとあたしは思った。
「それでお名前は何て言うのかな? 新しいパートナーさん」
「新しいパートナーさんって俺?」とんきょうな声にあたしは頷いた。
「みんなはクロウって呼んでるよ」
「クロウ?」
これがあたしとクロウの出会いだった。それから、クロウがずっとあたしに付いてきてくれるなんて思ってもいなかった。けど、クロウのおかげで随分と助かったのもホントだった。
「そう、クロウ。んじゃ、とっとと向こうに渡ってみるかい? 俺は行かないほうがよかったって思うと思うんだけどね〜」
「何で?」
「行けば判ると思うけど……。長居する場所じゃないな、少なくとも……」
「噂じゃね。悪魔の聖地とかなんだとか」しばらく黙ってたユメが口を開いた。
「ほ〜。やっぱ、それくらいじゃないとあたくし、柊まさきの冒険譚には物足りないよ」
「この根拠のない自信は一体どこから来るんだろうね?」
「うん? このおっきな胸の奥底から!」
「……別に大きくはないよな」
「……。何か言ったか、この野郎っ」
あたしは涙目。だけど、ユメは爆笑寸前。覚えてろよ!
「なぁ、二人とも痴話ゲンカはやめにしようね。みっともないから」
冷静なのはクロウだけか。あたしとユメはクロウの尻尾から背中に乗った。それだけでも随分と視点が変わって王様気分。高いところに上ったらえらくなったと勘違いするくらいに気持ちがいい。
「んじゃ、二人ともしっかり掴まっててね、落ちても知らないから」
また、クロウが無責任なことを言ってる。あたしはクロウに何か悪態をついてやろうと思った途端、離陸。ロケットエンジンでも乗っけてて、地球の重力圏を振り切るつもりなの? と勘違いしそうなくらいのGがあたしに掛かってきた。
「ちょ、そりゃ、クロウは何ともないでしょうけど、ちょっとはこっちのことも」
「考えないよ」文句の途中で早々と返事が来た。「だって、たったの一月分だぜ? そんな薄給で丁寧に離陸してやる義理なんかないねぇ」瞳だけ後ろを見て嫌な感じ。
「ねぇ、ちょっと、ユメも何とか言ってやりなさいよ!」
横を向いたらユメがいない。
「ねぇ、クロウ! ユメがいないよ?」
「あれ? 落ちたかな?」ひょんと首から先が下を向いて捜し物を始めた。
と、目標物を発見したらしくて、機首がグンと下がったような気がしたら、次には重力加速度よりも速そうな加速をつけての真っ逆さま。クロウ、あたしのことなんて忘れてるでしょう。ユメともども呪ってやるからな。
と、今度はユメの下に降りたのか急停止、ホンのちょっぴりの間滞空していると、ユメがストンと隣に降りてきた。
「クロウ。もう少しお手柔らかに頼むよ」
どうしてそんなに平気なんだ? もしかして、ユメって飛竜に乗り慣れてるの。
「もお、あたし、ヘロヘロだよ。垂直上昇、垂直降下……。最悪……吐きそうだし」
「こんなんでもう元気ないのか? まさきもたいしたことねぇな」
「うぅぅ、もお、それでいいですぅ」
いつもだったら、反論するんだけど、今はとってもそんな気分にはなれない。風邪を引いて朝からめまいの上、頭がくわんくわんしてるとっても気持ちが悪い感じ。でも、今度のは軽症、向こうに着くまでは直るかな。
「ハハ、弱気なまさきなんて滅多に見れないぜ、クロウ」
「へっ! 俺に声をかけたときそんだけしおらしかったら、嬉しかったのにね?」
「具合が悪いだけですぅ〜だ」あたしは思わずあっかんべー。
「でも、まだ、余裕があるみたいだぜ? クロウ、ちょっとアクロバチックに行ってみようか!」
「や、やめて、もう一回こんな目にあったら気絶しちゃうかも、かっこ悪いし、ホラ」
「冗談だよ」朗らかに笑ってる。
「てめぇら異様に元気だよな? 知ってる限り、大抵の連中はいやいやだったぜ?」
「だよな……。でも、まさきは違う、前向きで明るいよ」
「そりゃあね! どんなときもポジティブなのがあたしのポリシーなのだよ」
あたしは思いきり胸を張って、ドンと拳で叩いた。
「ポリシー? なのですか」不思議がったり、驚いた風でもなく、ユメはフーンという感じであたしの言葉を繰り返した。感じ悪いの。でも、悪気はないらしくて、どこかポヤンとした顔で向こうを見てた。と、
「ちょっと待って!」あたしは遙か北の方を指さした。何かが見えた。「ホラ、あれよ、あれ」
大断絶の北にアクアリュージョンに来てから見たこともないような巨大な人工物が見えた。橋だろうか。底なしの渓谷にどうやって架けたのか不思議なくらいの長さだった。
「ああ、あれね……」クロウがつまんなさそうにぽつりと言った。
「……鉄橋だよ」あたしは思わず、ユメに振り返った。「なんて目してるんだい? あれは俺たちが造ったんじゃない。前世紀の異物……だと、ヨウは言っていたけどな」
「鉄橋?」あたしは興味を引かれた。「クロウ! 行ってみよう」
「イヤだ」間髪入れず返事が返ってきた。
「何で?」
「生理的に嫌い」
「それじゃ、説明になってない!」
「だって、あそこにゃ、こわ〜い“親父”が住んでるんだ。用事もないのに行ったらさんざん怒られた挙げ句の果てにケチョンケチョンにされちまうよ」
「俺、そんなの初耳だ」ユメが言う。
「用事あるじゃん。あたしが会いたいんだ。十分すぎるほどの用事じゃない?」
あたしの言葉にクロウは難しい顔をして黙り込んでしまった。その“親父”によほど会いたくないのか、あたしが会いたいと言ったことに困惑したのか、後ろから見るクロウの瞳は微かな緊張感をはらんでいた。
「気が進まねぇんだけど……。そこまで言うなら寄ってみるぅ?」
クロウの恨めしげな視線があたしに突き刺さってきた。
「うん!」朗らかに言うと、クロウのどよよ〜んとしたふさぎ込んだ空気が伝わってきた。あたしはクロウの背中をナデナデしながら慰めた。
「いいよ。そんなに気ぃ遣ってくれなくても。そもそも、まさきを乗せたのが間違いなんだから」
ニヤリとしながら、クロウがやり返してきた。
「なんだ、結構元気なんでしょ。ちょっとでも心配して損しちゃったな」
流し目でちらりとクロウの眼を眺めてやった。
「心配なんて少しもしてないくせに。よく言うよその口は」
「あ……」あたしの瞳に映り込んだのはすっかり錆び付き、朽ち果てようとした巨大な鉄の残骸。向こう岸まで手を伸ばそうとして届かなかった雰囲気をもった哀れな鉄橋。長い年月の間に蔦からなにやら色んなものが絡みついていた。
「とっても、淋しそう……」正直そう思った。
「クロウたちと仲良くなれなかった連中はあの橋を渡ろうとしたさ。でも、あれを渡りきった奴らは誰もいない。谷越えの成功率は三割以下……、飛竜の機嫌をとれたやつだけ向こうに行ったよ」
「……理不尽。どうして、ジュンやレンのように世話をしてあげないの? クロウ」
「慈善事業やってるんじゃないだ。ま……ホントのところ、みんな向こうには行きたくないのさ」
あたしの頭くらいのでっかい眼がギョロッと後ろを向いてあたしを睨んだ。
「じゃあ、クロウは?」ちょっと可愛らしくしななんかつけてみたりして。
「……」呆れた眼差しに変わった。「まさきに脅かされたから」
「何か言いましたか? クロウさん」
めいっぱいの笑顔で微笑んだ。すると、よりいっそう呆れたようにクロウが続ける。
「アホか、てめぇは」
それから、クロウはぐんぐんと鉄橋に近づいて行った。ディテールが徐々にはっきり見え出すと同時におかしなことも判りだした。一体、どうやって組み上げたのか谷底までのびてゆく鉄骨の橋脚。ずっと地平線の彼方までのびてゆく錆びたレール。軌道の幅はあたしがよく知った日本の在来線のよりも幅広くて、新幹線が走れそうなくらいのものだった。
「あれ一体どこまで続いているの? 何が走っていたの?」矢継ぎ早に質問した。
「俺より、グリーンズの賢者さんたちに聞いて欲しかったな」ユメが苦笑する。
「あの時は知らなかったし、教えてくれなかったじゃない」ちょっとだけ憤慨。
どこかで分岐した二つの世界。その接点は意外と近い時代にあるのかもしれなかった。
「まさきがあの橋を見つけられるとは思ってなくて、あはは」
「誤魔化さない! ユメも忘れてたんでしょ?」
「まあね」おちゃらけてたのが急に真顔になった。「クロウと仲良くなれなかったとき、まさきにはあれを渡ろうとして欲しくなかった」淋しそうな笑み。
「え?」忘れてた訳じゃないんだ。
「今日はまだ静かだから判らないだろうけどね。ここの亀裂を吹く風はすごく強くて。特に橋の切れてるあたりはたまに台風なみの強風が吹き荒れるんだ。そんな風が吹いたときは谷間に共鳴して『竜の咆哮』が聞ける」
「あれが吠えたら人間なんかひとたまりもねぇな。吹き飛ばされちまう」
「……それがここを越えていくのがいないホントの訳さ」
あたしはごくりと唾を飲んだ。『竜の咆哮』聞いてみたい。好奇心が湧き上がってくると、お尻がムズムズとしてきて居ても立ってもいられなくなる。
「ね、ね、ねっ!」あたしはユメのシャツの袖を思い切り引っ張った。
「こら、破ける」
「いいよ、そんなの。それより、聞かせて?」
「……出たよ、まさきの破壊的な好奇心。誰か、止められる猛者はいないのか。クロウ、止めてみ」あきれ顔であたしを見たあと、ユメはコテンと転げてクロウの頭を見やった。
「俺は無理だと思うけどね。まさきの眼、爛々としてるぜ? もう、聞きたくて聞きたくて仕方がないだろう? それを止める自信ある? ユメ」
「ないね。でも、その親父のとこに行ってる間にいい時間になるだろ。風が弱い日でも絶対に聞こえる」
「ああ……気は進まないよ。どっちも」
後ろからちらりと見えたクロウの顔はひどく物憂げに見えた。
ユメは空を見上げて、クロウは無言で正面を見たまま、あたしは一人取り残される。あたしは二人にそんな難題を吹っかけたんだろうか? キョロキョロと二人を見比べてみても内心を探る術もなくて、風を切る音が聞こえてる。
「まさき……、あそこがたもとだ……」
ユメがずっと下の森を指していた。上から見た対岸の森よりは遙かに小さかったけれど、谷の際から続く北の山、ユメの言っていた果樹園の辺りまで連なっていた。クロウが風を切って一気に下降していく。みんな無口に、喋らなくなる。
「何でみんな、そんなに静かになるのよ。それも、クロウはともかくユメまで」
「たまには感慨に耽ったりするのさ」
「……似合わないよ、ユメ」
「うるせって」プイッてあっちを向いちゃった。
その間にもクロウは高度をドンドン落として、スゥ〜っと滑るように着地してくれた。
「ありがとっ! クロウ」
すると、クロウのでっかい目玉だけが後ろを向いた。
「何が? ……」ホンの束の間、クロウは考えて、はたと気付いてニヤリとした。
「ドスンて降りたら俺の頭に響くだろ? それだけ、まさきのためじゃない」
「ちぇ、せっかく、お礼を言ったのに。素直じゃないなぁ、もう」
「それはまさきだ。俺はこの上もなく素直、だぜ?」
「ウソ」あたしはボソッと言った。
「聞こえてんだよ、まさき。……ま、いいや、そこだ、そこ」
「だって、聞こえるように言ってるんだもんっ」えへへっと清々しく微笑んでみせる。
「いいから、早く降りろよ」憮然とした声色が返ってきた。「でないと追加料金!」
「だから、玉ねぎ一月分、やるって言ってるだろ」笑いながらユメが言った。
「玉ねぎは嫌いなんだよ。あの脳天につ〜んとくる辛さがいや」
「焼けばいいだろ? 甘くてうまくなるぞ?」
「どっちでもやなんだよ。何で、皮しかないもんを食わなきゃならんの」
「そう遠慮するなって」ユメがクロウの背中をバシバシ叩いていた。
「ねぇ、もう、いいかげんにしたら?」放って置いたらいつまでたってもやめそうになかったから、あたしは言った。「最初の目的、忘れないでよね」と言ったら、
「俺は忘れたかったんだけどな」クロウが半ば諦めたように囁いた。
「忘れちゃダメ! はい、行く。ってさ、その親父さんちってどこ?」
橋のたもと。森の際から地平線の向こうに消えていく鉄路があって、クロウのような大きな動物が住んでいるような気配は全くなかった。
「……実はさ、崖っぷちのちょっと下に行ったら横穴があいてる」
「じゃ、何でこんなところに降りたのよ!」あたしは腕を組んでぷんぷん憤慨する。
「心の準備をするためだ」
「誰が?」あたしはいつだって心の準備は出来てるんだ。
「俺がだよ。だってさ、親父怖いんだもん」急に、子供じみた口調。
「はぁ?」ちょっとがっくり。「だって、知り合いなんでしょう?」
「そおだけど……」
あたしはこの期に及んで駄々をこねるクロウを強引に説き伏せて、背中に乗った。まだ、ごちゃごちゃと文句をたれてるけど、ここまで来たらその“親父”に会わないことには気が済まない。クロウが滑空して谷間に降りると、確かに岩肌にくり抜いたような大きな横穴があいていた。
「そこ?」あたしはつい、クロウの背中をバシバシ叩いた。
「そこだよ……」うっそりしたやる気のない返事が返ってきた。
その直後、クロウは体勢を整えるとトトトっという感じで穴の中に着地した。中には灯りはなくて完全な暗がり。こう言うのあんまり好きじゃないな。あたしは隣に立ったユメの袖を掴んでいた。
「親父……」それは呟きのようで、いないことを願っているような響きだった。
「……クロウ。誰か連れてきたのか?」
薄暗がりの向こうに見えたのはよどんだ輝き。
「あれほど、客は連れてくるなと言ったはずだ」
「でも、親父。この娘たちがどうしても会いたいって言うから」
「この娘たちってどの娘たちだ? どんなに可愛い娘たちでもオレは会わない」
その間は声だけのやりとり。ただ、クロウと親父とのやりとりを聞いて、あたしは隣でユメがクスリと笑うのを感じた。
「……俺だよ、シャンルー。しばらく会っていないが、覚えているだろ?」
ユメの言葉に驚いたのはあたしよりもクロウだった。薄い暗がりの逆光中に前を見ていたクロウの瞳がくるっとユメを見てそのままハタと止まってしまった。それから、きっとホンの数秒だったんだろうけど、誰も喋られない奇妙に静かな時間が出来た。
「何だ、ユメか」つまらなさそうな無感動なちょっとつっけんどんな声。
「何だはこっちだよ。クロウが親父だなんて言うから誰かと思ったらシャンルーか」
「二人とも知り合い」あたしは思わず口を挟んだ。
「知り合いというか何というかだね、な?」
「ただの腐れ縁だ。そろそろ腐り落ちたかと思ったんだが、まだらしい」
「かけがえのない絆といって欲しいもんだけどね」笑いながらユメが言った。
「……」無言で、シャンルーの眼差しがあたしを突き刺した。「ユメ、そいつは――」ユメに向き直ってためらって、厳しい口調でシャンルーは言った。「セイの代わりか?」
笑いの消えたユメの瞳はシャンルーをしっかり見据えた。
「違うよ。そんなんじゃない」うつむいて、ユメの瞳が淋しさの色に染まった。
「そ、言えば、ユメ。そのうちセイのこと教えてくれるって」
「言ったな。そんなことも」どこか遠い目をしてユメは言った。「教えてやるよ……」
ユメの顔がひどく切なげに見えたのはあたしだけだったのかな。声が急にトーンダウンしてあたしを見てくれなかった。目線は地面を張って歩いてるみたいにうつむいてる。そして、さっと顔を上げてすごく儚い笑みを浮かべて、でも、きっと、それがユメの精一杯の明るい笑顔だったんだ。
「……セイは“挑戦者”と一緒にいてベリルの子供に殺されたんだ。――挑戦者を守るためにその子の親を刺したのさ。……もお、言いたいことは判っただろ?」
淋しげにユメの瞳が揺らいでいた。どっちが正しくて、どっちが間違ってるだなんて言えなかった。フゥの世界だって、きっとどこかで同じことが起きている。でも、こんなに近くでこんなことがあると胸が詰まって言葉がなくなる。テレビで遠く離れた出来事を他人事のようにみて感じるのとは全然違うんだ。
「三年くらい前にね。生きてりゃ俺の二つ下だから、まさきと同い年の時か……」
「十八の時?」あたしは訝しげにユメを見詰めていた。
「十八だ。セイが初めて剣をとったのは六つの時。へへ、よく覚えてるよ」
けど、ユメがセイへの思いを語ることはなかった。そのうちの“そのうち”は今じゃないんだね。それとも……ま、いいや。ユメとあたしの関係が変わらなければそれでいい。思い出して辛いのはあたしじゃなくてユメなんだものね。
なんて考えているうちにユメはいつもの調子を取り戻していた。
「と言うことで、今晩、ここに邪魔していいか?」
「ダメだと言ったところで、どうせお前は居座るつもりなんだろう?」
「さすが、伊達に腐ってないね」
「ユメがガキの頃からの付き合いだからな……。思考パターンぐらい読める」
「随分、長い付き合いなんだね! それはそうと、ね、ね、ユメ?」
呼びながらユメの袖を引っ張った。
すると、ユメはとってもいやそうな目つきをしてじと〜っとあたしを睨んだ。
「……まだ、覚えてたんだ?」
「一度、火がついたら一時間やそこらじゃ忘れませんって」
「だろうなぁ〜。記憶力はすっごく良さそうだもんね。細かいことまで忘れないだろ?」
「ど、言う意味、それ?」じとっと睨んで嫌味たっぷり。
「純粋に褒めてるんだけどね? まさきって捻くれてる?」
「ひっ、捻くれてなんかないもん!」
「ぷ〜っとふくらんじゃってフグみたい」
「フ? し、失礼な! クロウ、こんなやつ、放っておいて行きましょう」
一度、女の子の機嫌を損ねると大変なんだと思い知らせてやる。と意気込んでみても、悔しいけれどユメには全然通じないんだろうな。
「じゃあ、仕方がないから外へ出ようぜ。咆哮はここより開けたとこがよく聞こえる」
「だな……」
結局、二人とも渋々だったけれど、動き出してくれた。そして、外の空気はやっぱり塞ぎ込んだようなシャンルーのいる洞穴よりも格段に清々しく感じられた。よどんだ空気よりも流れている空気の方が澄んで綺麗なのは間違いないよね。
「まさき。今が凪だ。ほぼ無風状態だろ?」ユメの瞳があたしを見た。
「うん、でも、――陰でクロウが吠えてるとか、シャンルーが啼いてるとかはなしね?」
「何でわざわざそんな演出しなくちゃなんねぇの、俺が」
もお、呆れるのにも疲れてしまったようなやる気のない視線があたしを見ていた。
「……海側から吹く風と、山側から吹く風は微妙に音色が違うんだ」
「今はどっち?」
「海から……吹く風。竜の勝ち鬨。その逆は竜の雄叫び……」
ユメの眼差しがにわかに真剣になった。谷から少し距離を置いて見ているのに、そんな顔をするなんて竜の咆哮はかなり危ない物なんだとあたしは感じた。
「来たぜ、まさき。……竜の咆哮」
「でも、ホンのそよ風だよ?」
「ここら辺はね」疲れた笑い。「凪だから、初めはそよ風から」
ユメの言ったようだった。来た。初めはそよ風。やがて涼風。あたしたちのいた辺りではそれくらいで最大の風量のようだった。でも、あっちは違う。断絶は深すぎて、下の様子はわからないけれど、何か空気が変わったような気がしていた。穏やかのんびりムードがピンと糸を張ったような緊張感に変わっていく。ザワザワと身の毛のよだつ嫌な気分。
「どうした? まさき。顔色が悪いぜ」
「もしかしたら、怖いかも?」
ォォォオォオオオオオ。谷間の岩に風が反響する。風が猛り狂ってる。風が鳴いて、竜が吠える。初めてなのに何か懐かしい。あたしはどこかで聞いてる。でも、どこで? 記憶のずっとずぅ〜っと奥底で誰かが呼んでる。
「聞いた?」意識が記憶の向こうに吹き飛んでいたのをクロウが呼び戻した。
「う? うん……」ちょっと驚いてしどろもどろ。
「あとは風が強くなったり弱くなったりして、微妙に音色が変わるんだ。今日は……風が弱いから、特大級の音量は期待薄だ。もどろうよ」
「うん……」
返事をすると、クロウの頭がくんと下がってゆっくりと下降を始めた。
そんな中、あたしは夕暮れが迫ってくる空のもとで風の音を聞いてる。不思議な感じ。心地のいい風があたしの頬を撫でて、髪をなびかせていく。遙かな大地には森が広がっていて、視界の外れの方にマルーンヒルがあった。
「あたし……遠くまで来ちゃったんだ。帰れる……の、かな?」
「らしくないぞ。前までは帰れなくても帰れるって信じてる。そんな勢いがあったのに」
心配そうなユメの眼差しが痛い。あたしだってただの人なんだ。哀しく、淋しくなることだってあるって言いたかったけれど、黙っていた。
「そんで、さ、シャンルー。今晩よろしく頼むよ。ここなら変な輩も来ないし」
「好きにしろって言ったはずだが……?」片目を開けてまんざらでもない様子。
「じゃあさ、まさきにアクアリュージョンのこと聞かせてやってよ。俺ちょっと出てくるから。クロウ、そこまで付き合ってくれ」
「いや」寝耳に水だったようだけど、あっさりと断るのはクロウらしいかも。
「嫌じゃ、ねぇんだよ。いいからつきあえ」
「俺の晩飯はどうしてくれんだよ?」
「晩飯? そんなもん嫌ってほど食わしてやるから。来い!」
結局、ユメは無理矢理クロウの背中に乗って外に飛び出していった。
「……泣きに行ったな、あれは」
「泣きに行った?」あたしは訝しげにシャンルーの横顔をのぞき見た。
「ああ、もうどうにも我慢できなくなったんだろうな。まさきはセイによく似ている」
シャンルーの言葉を聞いてあたしは思った。あたしは……妹なんだ。セイと同じことにならないで欲しいからユメはいるんだ。セイを亡くしたユメの気持ち。まだあたしの知らない気持ち。身近な誰かが急に遠くに行ってしまったことのないあたしには判らない感情なのかもしれない。今のあたしにはユメを慰めることさえ出来ないんだ。
「あたしは……セイの代わり?」
「――それはユメに聞いてみろ」
あたしはシャンルーにぼふっと身体を埋めた。がさがさしててちょっと硬い。クロウはもう少し柔らかかったから、シャンルーは年上なのを感じさせた。