13. droping of "time"(零れ落ちる時の雫)
「……怖い……」
薄暗い地下牢の中でジェットは呟いた。怖いのだ。近ごろ、自分が自分でなくなっていくような奇妙な感覚を色濃く抱くような気がしてしまう。確かにいつの頃から、ここから出られなくなってしまったのかは記憶にはない。けれど、自分が失われるという感覚には一度も襲われたことはなかった。それなのに今は、自分の中にもう一人の自分がいる。
そして、そいつはジェットの心を鷲掴み、壊そうとしているかのようだった。
それも、そいつの行いがジェットにもそこはかとなく感じられる。完全に遮断された感覚ではなく、自分以外の人格が自分の意思とは無関係に自分の身体を勝手に動かす。記憶の彼方にそいつのやってきた行いが残っている。自分が手を下したと言う感覚は無論ない。けれど、見えていたその視界はどう考えてみたとしても、他人として見た映像ではなく、明らかに自分自身として関わり、動いたものにほかならない。
「――うぅ……、わたしは……わたしはどうなってしまうの……」
ジェットは地下牢の壁際に力なくうずくまっていた。
*
迷夢はクアラパートの教会をあとにしてそのまま次の目標に向けて行動を開始した。アリクシアは生きている。クアラパートのエルフの老司祭はその隠れ家を教えてはくれなかったが、おおよその見当はつく。大きな魔力を隠すことは容易ではない。だから、木を隠すのならば森の中で、自然界の魔力の集積地帯に姿を隠すのがベストなのだ。そう考えれば、アリクシアクラスの魔法使いが隠れられる場所など限られる。
リテールに限定したら、エルフの森、黒き湖、風の双塔、サラマンダーズバックくらいだ。しかも、その全ては精霊の住み処であるだけにアリクシアの隠れ家から除外できる。また、ヒトの集まる都市部では大きな魔力を完全に隠せるような場所はない。
従って、迷夢が下した最終判断はドラゴンズティース、その場所だった。
「リテール協会アリクシア派。レルシア派初期への回帰を目標につくり。のちに追放され、クアラパートでトリリアンを設立。……ここまではいいとして、ドラゴンズティースをひらくまでには何があったのか……」
想像をしたら、いくらでもロクでもないことばかりが思いつくが、迷夢自身が思いついたことのほとんどはあり得ないことだと思うくらいだ。宗教の宗教たる由縁を大切にしたトリリアンをひらいたアリクシアが何故、一種、邪教と呼ばれたドラゴンズティースをひらいたのか。ドラゴンズティースとは秘境・ドラゴンズティースに埋没した竜の牙や怪しげなものを使い、揚げ句に生贄まで要求する邪教であり、竜との婚約の証である“女神の翼”をもたらす、まさに力こそを重要視する宗教だった。
と、考えている間にリテールでも有数の山岳地帯・ドラゴンズティースに迷夢はいた。
「……ドラゴンズティース……か」
短い言葉のうちに多分の憂いが含まれる。迷夢は空から降りると、ごつごつとした岩場をのんびりとした足取りで歩き出した。しかし、その眼差しはあちらこちらをしっかりと観察していた。迷夢の考えが間違っていなければアリクシアはここにいる。
「――とは言え、ドラゴンズティースもだだっ広いのよねぇ……」
その広い山岳地帯を捜し回るかと思うと、多少やる気がそがれてしまう。魔力が集積している場所を選んではより注意深く探りを入れるが、向こうも魔法使いであるだけに迷夢がかぎ回っていることくらいすぐに気取られてしまうに違いない。
「あたしはアリクシアと出会えるのかしら。それとも、アリクシアが出会ってくれるのかしら」ぶつぶつ。「まー、あれよねぇ。運次第……」
迷夢はヒトが隠れていられそうな場所をくるくると捜し回った。やはり、向こうが姿を現そうと思わない限り、見つけ出すのは不可能なのだろうか。迷夢は気力を無くしそうになりながらも、まだ頑張っていた。と、迷夢は何か強力な魔力を持った存在を感じ取った。
そこにいる。その岩陰にひっそりと。
「――アリクシア……?」
「……やはり、迷夢、あなたが来たのですね」
「あら?」ちょっぴりわざとらしく迷夢は言う。「あたしとしては意表を突いたつもりだったんだけどなぁあ?」そして、さらに不敵に笑みを浮かべさえした。「流石は――ドラゴンズティースの教祖さま……というべきかしらね?」
揶揄を込めて迷夢は言う。
「……あなたはどこまで知っているのですか?」
「さあ? ま、あたしはどこまでも限りなく知っているわよ」
はったりなのか本気なのかよく判りはしない。けれど、黒翼の迷夢と言う名はよく聞く名前であるし、その風貌まではアリクシアも知っていた。十二の精霊核の伝説に終止符を打った天使の一人。アリクシアは当時、外部との接触を完全に断っていたから、その実、その時に起こった詳細までは把握していない。
「限りなく、際限なく様々なことを追及する悪夢のような存在とは聞いたことがあります。子どものような好奇心に、行動を起こせば止まらない悪魔のような天使」
「それはもちろん、褒め言葉と受け取ってもいいのよねぇえ?」
「褒め言葉? あなたがそう思うのでしたら、そうなのでしょうね」
「まあ、いいわ。ちょっと、あたしと一緒に来てもらえるかしら?」
「何故……?」アリクシアは無表情、無感動に答えた。「わたしがあなたに従う義理はありません。わたしはわたしの思うがままに……」
「キミがキミの思うがままで構わない。けれど、ちょっと、付き合って欲しいのよね」
「腹黒そうなあなたに付きあうつもりはありません」
「ふふ、そおかしら? ま、キミがどうしてトリリアンを見限ったのか。そして、ドラゴンズティースなんて怪しげなものを立ち上げたのかなんて、興味はあるけど、この際、そんなのあとでいいのよ。あたしとしては」
「……どうでも良いのなら、わたしのことは詮索しないで欲しい……」
「現状、この有様で放っておけるはずがないでしょう? あたしが言いたいのはつまり、キミが何故、トリリアンを……じゃなかった、ドラゴンズティースを開祖したかじゃなくて、事態の収拾をつけるのに手を貸せってことよ」
「何故……?」アリクシアは再び冷たく問う。
「そうね。確かにキミにはあたしたちに手を貸す義務も何にもない。だけど、魔法の使い手としてキミはこの件に首を突っ込まない訳にはいかないのよ」
言っていることが支離滅裂だが、迷夢の真剣な眼差しを見ていると言葉とは裏腹な奇妙な説得力に乗せられてしまう。かと言って、アリクシアは迷夢の口車に乗るつもりはなかった。確かにトリリアンを作り、ドラゴンズティースを開祖したかもしれないが、現状のある意味の混乱を招いていることとは直接は関係がない。
「質問の答えになっていないと思いますが……?」
「大丈夫。まだ、一つも答えていないから」迷夢は悪辣な笑みをたたえる。「で、キミがあたしに手を貸さなければならない理由だったわねぇえ? ……教えてあげないっ!」
「教えていただけないのなら、わたしは動きませんよ」
全く冷静な態度でアリクシアは迷夢に対抗する。こう言った冷静な態度をされるとかえって迷夢は戸惑ってしまう。相手のスタイルを崩してつけ込むのが迷夢のスタイルだけに、崩れない相手だと対応に苦慮してしまう。
「あ〜。何か、キミが相手だとやりにくいのよねぇえ? もう少し、何と言うか、普通に明るくポジティブにいかないものなのかしらねぇ?」
「そう言われても、これがわたしの普通ですからね」
「そお……」流石の迷夢もそこまで言われると諦めざるをえない。
ベリアルといい、アリクシアといい、トリリアンに関係するヒトたちはどうしてこうも扱いにくいのだろうと迷夢は思った。そもそもその迷夢自身が他のデュレやベリアルたちに扱いづらいヒトと思われているとは露ほどにも考えていない。
「じゃあ、どう言ったらキミは納得してあたしについてきてくれるのかしら?」
策を弄するだけ無駄と悟るや否や迷夢は単刀直入路線に転じた。
「あなたがどう頑張ったとしても説得には応じませんよ。わたしは現し世には興味はありません。ドラゴンズティースを開いた理由こそお話ししても構いませんが、あなたとともに――何かは知りませんが、事態の収拾に赴くつもりはありません」
「あーそう」
迷夢は仏頂面で腕を組むと、そっぽを向いた。条件が厳しい。フツーの相手なら、この辺りで面倒くさくなるのか大概は折れてくれるのだが、アリクシアはそんな様子をおくびにも出さない。かなりの難敵だ。ここまで来ると、話し合いの席で穏便に事を運び、アイネスタでの戴冠式の席上に登場してもらうことは出来ないのだろうか。
「――そこまで言うのでしたら、トリリアンに未だ籍を置くエルフのベリアルとあってみてはいかがですか? あの娘なら、あなたとも波長が合いそうな気がしますし。……むしろ、危険にアクティブならハイエルフのサラと接触してみてはどうでしょうか?」
「……ハイエルフのサラ?」
ベリアルは当然知っている。けれど、サラの名は初めて聞いた。
「ええ。ですが、もう、ここ数百年は会っていませんから、どうなっているかまでは知りませんが、あなたがトリリアンについて何かの収拾をつけたいというのなら、わたしよりもむしろ、そちらの手を借りたほうがよいでしょうね?」
アリクシアはにべも無くさらりと言ってのける。そうしたら、軽くあしらわれて“はい、そーですか”と大人しく引き下がる迷夢ではない。しかし、今、何を言ってもアリクシアを説得するのは困難極まりない。かといって、実力行使に出ても面倒くさいことになるだけのような気もするし、お互いに無傷ではすまないのは確実だ。八方塞がりとはまさにこのことを言うに違いないと迷夢は思う。
「むぅ。――どうしようかなぁ……。――今日中にもう一個、片付けたいことがあるし、……とりあえず、キミの提案で妥協するしかないのかしらねぇえ?」
迷夢は上目遣いにアリクシアを見やった。
「――わたしは妥協しませんよ」
「……。そ。じゃ、あたしが我慢するしかないのね……。けど、まぁ、あたしは諦めたワケじゃあないからね」迷夢はズビシとアリクシアを指さした。
*
非常に残念だったが、迷夢はとりあえず、アリクシアを自分の陣営に引き込むことを諦めて、次の行動に移った。アリクシアのことにかまけていられるほどの余裕はない。優先順位を入れ替えてでも、様々なことを片付けていかなければ、追いついていかないのだ。
そして、今日中に何とかしたいことの一つとは黒い翼の天使、そのものだった。
ベリアルの情報を元にすると、次に黒い翼の天使が現れるのはテレネンセス、アルケミスタより北部の街になるらしい。実際のところ、天使がどこへ派遣されるかは完全にヘクトラの気紛れでその時、その時に指示を出すようだ。それ故、ベリアルも組織の上の方にいながら、天使を使う“戦略”は一切判らない有様なのだという。
「――あのベリアルがこの様なんだから、どうしたものかしらねぇえ?」
迷夢は独り言をぶちぶちと言いながら空を舞う。天気は快晴。視界は良好。何者かが上空に現れれば、何事にも邪魔されることなくすぐに発見できるだろうし、そうでなければ、さすがに困る。迷夢が相手をする相手はどうやすく見積もっても天使なのだから。
「し・か・し、ここまで平穏だと、退屈よねぇ……」
ヒョウォオオオォォォオォオオオ。
風。冷たい風が吹き抜ける。流石に寒い。迷夢は上空から降りてくると見晴らしのよさそうな高台に陣取ることにした。とは言え、暇だ。手に入れた情報はかなり曖昧で、この辺りに現れそうな時刻も判らなければ、正確な場所すら判っていない。だから、もしかしたら待ちぼうけを食わされるだけで今この貴重な一日が過ぎ去ってしまうかもしれない。
しかし、未だジェットの隠れ家を掴めない以上は避けられない。
「……何か、名案はないものかしらね……」
迷夢は呟きながら、じっと空を見上げていた。
と、視界の彼方から何ものかが高速に移動してくるものがあった。よく見ると黒い翼に黒い髪。それは迷夢の捜してやまないジェットの姿にほかならない。迷夢は物音を立てないよう、さらにジェットの背後に回れる位置からスッと上空に舞い上がった。
「のうのうとのさばっていられるのも今日までよ。この前のようにはしないからね」
迷夢はかなりの間隔をあけてジェットの背後をとった。
「……ここがミーシャラの街だな?」
黒翼の天使は全く感情のこもっていない抑揚のない声で言った。何をするにもたいした感慨も、おもしろさも湧き上がってこない。ただ淡々と、そつなく“仕事”をこなし、それ以上のことはあまりするつもりはない。
その様子は背後に回った迷夢にもひしひしと感じられた。
「……そうね。ここはミーシャラの街よ」
誰もいないはずの空間から突如、返答があった。ここに到着するまで空には一点の曇りもなく、同時に誰かが近くにいるような雰囲気は全く感じていなかった。
「誰だ、お前は」至って普通の質問をする。
「ついこの間、キミとは一戦を交えたような気がするんだけど、あたしの気のせいだったのかしらねぇ?」
「……お前の気のせいだろう。わたしは……お前など知らない」
「知らない?」迷夢は素っ頓狂な声を上げた。
知らないはずはない。迷夢とジェットはユーリスカの上空で視線をかわし、テレネンセスからアルケミスタへと至る道筋で確実に一戦を交えたのだ。あの不穏極まりなかった戦いを忘れるなんてあり得ない。
「何で、あたしを知らないの? あたしとキミは一度出会ってる」
そう言うと、ジェットはどこか不可思議そうな表情を迷夢に向けた。素で覚えていない。それは逆に迷夢にとって予想外だった。呪術に支配されている時とそうでない時を挟むと記憶が飛んでしまうのだろうか。だとすると、恐ろしい。今までに自分のしてきたことを全く理解せず、記憶に蓄積することもなく機械的に街を破壊しているのだとしたら。
「――出会っている……?」訝しげにジェットは問う。
「そう、あれを出会ってるというんだったら、やっぱり、出会ってるんでしょうね?」
迷夢は不機嫌さを露にしつつ、ジェットを睨みつけた。やはり、面白くない。ユーリスカの上空でしっかりと印象づけられたと思っていたのだから。
「まあ、今更、ぐちゃぐちゃ言っても意味なんかないわよねぇえ?」迷夢は心を落ち着かせるかのように大きく深呼吸をした。「あたしは迷夢。一言で言うとあたしは……あなたを救いに来た――。そう言う事にしておいて」
「そう……。わたしはお前を倒しに来た――」
「キミはそれでいいの。あたしが勝手にそう思ってるだけだから」
「そう。じゃあ、わたしはわたしの勝手にやらせてもらう。――だから、邪魔するものはここで消えろ。黒翼の天使はわたし、一人だけで十分だっ!」
ジェットは虚空からブロードソードを呼び出した。そして、そのまま猛進する。迷夢もジェットの行動をほぼ読み切り、自分の得物、レイピアを呼び寄せていた。
ギィイィィィィイイィン。激しく火花が散る。
「あたしにケンカを売るなんていい度胸をしているわ」迷夢は言う。
「売られたケンカを買っただけだ」
「そう、買っただけなのね。じゃあ、そのお買い物に満足してもらわなくちゃあねぇ?」
迷夢は不穏ともとれる発言をしながら、ジェットに突撃した。ジェットは何としてもここで仕留めたい。期成同盟が最後の詰めに向けて活動を始めたことくらいはトリリアン総長の知るところになっているはず。としたら、さほど間をあけずにジェットを投入してくるのに違いない。それが現実となれば、期成同盟軍は圧倒的に不利な立場に立たされ、迷夢の思い描いた方向に物事を進められなくなる。
ギャリィイ。耳障りな金属音が響く。剣と剣をせめぎ合わせ、二人は睨みあった。
「その程度ではわたしには勝てない」無表情にジェットは言葉を連ねた。
「そう、その言葉、そのままキミに返してあげる」
迷夢は交叉した剣を強く押して、一気に間合いを広げ直した。呼吸を調え、短時間で決着をつける。ジェットもそれなりに強いだけに長期戦にもつれ込んだら、迷夢には分が悪い。ジェットは迷夢が死のうと何しようと構わないので手加減なしで攻められるだろうが、迷夢はそうはいかない。ジェットを無傷、とは言わないものの少なくとも、あまり怪我をさせないうちに確保しなければならない。
「――わたしではお前に勝てないと……?」
「そうね。キミじゃ、あたしには勝てないわね」不敵に言い放つ。
どんな逆境、不利に立たされようとも迷夢は必ず“勝ち”を宣言する。そうすることで絶対的不利を覆すべく燃え上がるというものだ。そして、実際、現状ではジェットを助けたいと考える迷夢が有利になることはあり得ない。
「そうか、わたしではお前に勝てないか……。では、今、無理をしてお前と争っても時間の無駄のようだ」ジェットは相変わらず抑揚のない無味乾燥な冷たい声色だった。「……ミーシャラを潰すのが至上と言うのでもないから、この次、お前がこの場を嗅ぎつけられなかったときにとっておくことにしよう。――パーミネイトトランスファー!」
「あ、こらっ、逃げるなんて卑怯だっ! ちょっと、売られたケンカを買ったんじゃなかったの〜? ちょ、買ったものを放置するのはやめてよねぇえ?」
と、迷夢が喚いたところでジェットは全く意に介することなく姿を消した。
*
エスメラルダ期成同盟がいよいよ本腰をあげて、王国再建への道筋をハッキリつけようと様々なアクションを起こし始めたころ、トリリアン、アルケミスタ教会の礼拝堂でヘクトラとクローバーがあいまみえていた。
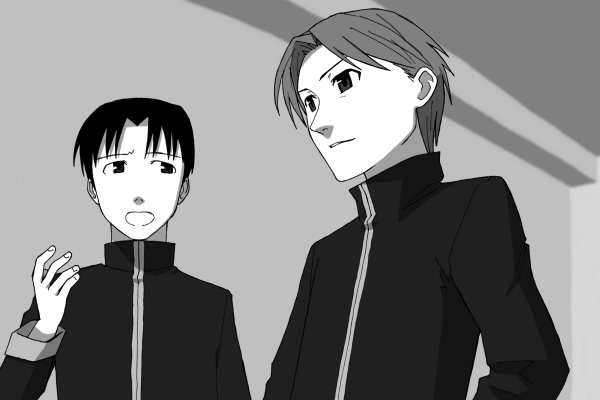
「クローバー、エスメラルダ期成同盟もいよいよ動き出したようですね……」
「そうですね……」クローバーは淡々と答える。
「お前は少しも驚かないのですか?」ヘクトラはホンの少しの違和感を覚えた。
「ええ。――驚くと言うよりはむしろ、自明だと思います」
期成同盟が本腰を入れて動き始めるなど予想の範疇だ。天使を使い、あちらこちらの街を潰して回れば、自らの版図になるだろう街のために動くに決まっている。そして、その目的は待ちの人々を守るためだけではなく、当然、トリリアンを屠るために。
「自明……ですか……?」ヘクトラはクローバーに問う。
「自明です。あなたがジェットを使い罪のないあちらこちらの街を無作為に破壊させるからです。――わたしたちのガーディアンクラスが何かしらを起こせば、基本的には協会が軍隊を組織して、それでも……と言う時には期成同盟が助太刀と動いていました。が、ガーディアンを抑えるということ以外は手を出していなかったはず……」
「ふむ。つまり、わたしたちはやり過ぎたといいたいのですね? 協会の権威を失墜させ、トリリアンこそが真の信仰対象であるべきと認知させるべくやってきたつもりではありますが、ここに来て性急に物事を進め過ぎたといいたいのですね? クローバー?」
ヘクトラは反論を挟む余地を残さぬようにクローバーを詰める。
「ジェットを戦線に投入したことで期成同盟盟主を本気にさせ、その活発化を招いたといいたいのですね」畳みかけるようにヘクトラは言う。「――ですが、それは期成同盟の結成理由を予め心得ていれば、予想の範囲内。遅かれ早かれ、事実上の覇権を握るリテール協会、もしくはトリリアンの既得権を奪い国家としての体裁を整えられるような作戦をとることでしょう。今更、お前に言われるまでもありません」
「……左様ですか……」
「わたしはチャンスを作ったのです。いいですか、クローバー。わたしたちはこのリテールに根差し、必ず復活を遂げるのです。アリクシアさまが目指した協会を今、この時代に実現させるのです。それが……アリクシアの供養にもなるのです」
どこでゆく道を違えたのだろう。クローバーはフと思った。確かにヘクトラには以前から妄想僻をもっているような節があった。けれど、病的と言うほどでもなく、さほど、気になるほどでもなかったことは間違いない。それが虚言癖とも妄想僻ともとれ、一歩間違えばとんでもないことになりそうな雰囲気を醸し出したのはいつごろか……。
やはり、妹のアリクシアが亡くなったあとからだろうか。
「アリクシアのために仰るのなら、アリクシアの思ったように進めてください」
「何を言いますか、クローバー。わたしはアリクシアさまの理想の実現のため。歴代総長の本懐を遂げるために行動しているのです。それがアリクシアの思いを受け継ぐことになるのです。トリリアンは必ず――リテールで一番の宗教になるのです」
「一番に……ですか……」
その言葉はクローバーの心のうちに虚ろに響いた。
「一番になることがそんなに重要なのですか?」
「その通りです。一番でなければ意味がありません。あなたは知らないのですか? リテール協会がその初期から現在に至るまでリテールで絶大な影響力を誇るのはその巨大さ故。エスメラルダ王国さえ凌駕し、滅んだ後も民衆の拠り所として……。諸外国は認めていませんが、事実上この地域の国家権力を代行するに至ります」
「――それが、わたしたちと何の関係があるのでしょうか?」
クローバーは敢えて問う。返ってくる回答など判り切っているが、今まで直接聞いたことがない。だが、万に一つくらいの確率でまともな答えが得られるかもしれない。
「関係性と言う話になるのなら、関係ないでしょうね。――しかし、わたしたちが目指す先には協会があります。クローバー、あなたのニュアンスを読み取るなら、協会は良くない行いを数々してきたことでしょう。ですが、それだけに囚われてはいけません。表に目立ったことだけではなく、隠れた一面にも目を向けなければ、真実を見失います」
言っていることは恐ろしいほどに正論だ。ただ、それは本当にアリクシアの目指したトリリアンと重なるのだろうかと疑念が残る。むしろ、そんな協会を反面教師にして立ち上がったのが協会アリクシア派で、トリリアンではなかったのだろうか。
「――何か、問題でもあるのでしょうか?」
「……いいえ」クローバーはそれ以上の追及はやめた。
今のヘクトラには何を言っても、届かない。ならば……言葉を投げ掛ける必要はない。こうなってしまったなら、クローバーも密かに袂を分かとうとしているハイエルフのサラのように振る舞ったほうが得策なのだろうか。それとも何を考えているのか全く判らなく飄々とした態度を貫くベリアルのようなのがいいのだろうか。
「――他にご用がなければ、わたしは失礼いたします」
クローバーは少しばかりよろよろしながら踵を返した。
「そうですか……。ところで、お前はどちらの側につくつもりですか……?」
「き、急に何を言い出すのですか……」動揺は隠せない。
「急にではないと思いますが。……近頃はサラの挙動も気になります。ベリアルの飄々とよそよそしいのは以前からなので、企んでいるのか地なのかはいまいち判別がつきかねますが、少なくともお前が悩んでいることくらいは判ります。小心者のお前のことですから、期成同盟に寝返ることはないと思いますが、サラや、ベリアルのような連中に靡かないとは言えないですからね。さて、どうでしょうか?」
爽やかな笑顔の裏に隠された悪魔の微笑みを垣間見たような気がする。
「――別に彼らはトリリアンを裏切っているわけではないと思いますが……?」
「確かにトリリアン“は”裏切っていないかもしれないですね」
そこでクローバーはハッと気がついた。ヘクトラは気がつかない振りをしているだけで、トリリアンの内情をおさえている。期成同盟や協会との抗争に勝ち抜くつもりでいて、勝ち抜いた後に粛正を行うつもりでいるのかもしれない。
「もちろん、クローバーは最後までわたしについて来てくれますね?」
優しそうなヘクトラの笑顔の向こうに一体、何が隠されているのだろうか。クローバーは空恐ろしげなものを感じながら、無意識のうちに小さく頷いていた。
*
その時、ジェットの額に朱色の文字が浮かび上がった。誰かに呼ばれたような感覚もある。そう、いつかもこんな感覚に支配され、ガラスの向こうから自分ではない自分がすることを見せつけられる。その後は……ハッキリとした記憶は残っていない。
「うう……。わたしは……。わたしは……」
ジェットは頭を抱えて床にうずくまった。頭に鈍い痛みを感じる。それは頭頂部から徐々に広がるような感覚を覚えさせ、広がると同時に眩暈のような感触を味わわせる。それから、意識が遠のいていく。
「あ……」ジェットは短く悶えた。
そして、先ほどまでの苦しみを脱したかのような凛々しく冷たい表情を取り戻すと、ジェットは片膝をつき、ゆっくりと無言のままに立ち上がった。左手を軽く額に当てて、頭痛が消えたことを確認するかのように頭を左右に振った。気分はすこぶる良い。光を失いどこか虚ろに見えるその瞳は冷徹な空気を醸し出していた。
「――ジェット……。お前は静かに眠っているがいい……」
ポツンと呟くように言葉を残すと、ジェットは戸口へと足を向けた。
文:篠原くれん 挿絵・タイトルイラスト:晴嵐改
