10. please, trust me (信じてください)
閉ざされた地下牢に転がる一体のぬいぐるみ。古ぼけてしまい、所々にほつれのある、どこか薄汚い一体のウサギのぬいぐるみ。その赤いボタンの瞳はじぃ〜っと入口を見詰め、誰かが帰ってくるのを待ちわびているかのようだった。
キィイィィィイィ。錆びついた音を立てて扉が開く。
そして、不気味な暗がりに薄暗い光がさーっと射し込んだ。
「わたしは……この世界の全てを手に入れる……。あぐっ」
と、不意にその額に記された朱色の文字が浮かび上がり、一瞬、燃え上がるかのような激しい光を発した。それは強烈な痛みを伴ったようで、人影はよろめき、片膝をついた。
「……? わたしは……何を……?」
先程までの異様なまでに鋭い眼光はなりを潜め、か弱い乙女の色を醸していた。それから、人影は壁際に歩み寄り、ぬいぐるみをそっと手に取った。
「……ただいま、わたしのウサギちゃん……」
ぎゅっとぬいぐるみを抱き締めて、黒い翼の人影は今日の眠りについた。
*
「それで結局何がどうだったのよ?」
迷夢は苛々したような刺々しい口調でベリアルに問うた。ベリアルが知っていて自分が知らないことがあるなんてことは迷夢のプライドが許さないのだ。
「ですから、今からお話します。少しは落ち着いてください」
むずかる子供をあやすような話しぶりでベリアルは言う。
「むー。それはキミの言う通りなんだけど、早く知りたいじゃない? 知ってそうで知らないデュレの過去なんてさぁあ?」
迷夢は瞳をキラキラ煌めかせて、ベリアルを見やる。
「それは、まあ、そうなんでしょうが、人の過去に興味を抱くなんて……」
「お下品とでも言いたいんだろうけど、この際そんなことは言っていられないでしょう? 小耳にはさんだ限りじゃあ、あっちの方は全面解決はしていないんでしょう?」
迷夢は急に真顔になった。さっきまでのふざけた態度とはほぼ正反対、ベリアルでさえ驚くほどの変わり身だ。とりあえず、「あっちってどっち?」と意地悪をしたい衝動に駆られたが、そこはぐっと我慢する。
「確かに迷夢さんの仰る通りですけど……」
「じゃ、話して。時間がないのよ。この作戦行動中にデュレに何かがあったらめでたく一巻の終わりなんだから頼むわよ、ベリアル? というかさぁあ? 今度のことを上手に使ってデュレの心の傷を大人しくさせることが出来るんじゃないかなぁと思って。端的に言えば、“パワー”なんでしょ。本人が気が付いていない尋常ならざる“パワー”をどう制御していくかってことよねぇえ? つまり?」
おおよその筋はあっているのだが、どこからそんなことを類推してきたのかさっぱり見当もつかない。ここまで来ると、掛け値なしに迷夢の洞察力、情報収集力、その他諸々のことに感心するし、ただただ驚くばかりだった。
「はぁ……まぁ、そんな感じといえば、そんな感じですが……」
何かよく判らないが、迷夢の迫力におされてベリアルは渋々話を始めた。
「――では、迷夢さん、『女神の翼』をご存知ですか?」
「女神の翼って、キミ、デュレのことひん剥いたの?」
急にとても嬉しそうに迷夢は言った。
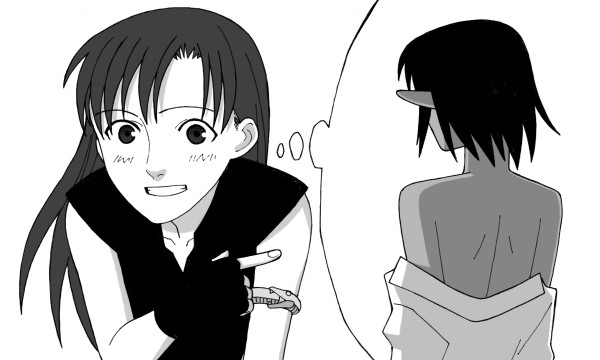
「ひん剥いたって……。そんな卑猥なことはしていません」
「あら、残念。まぁ、冗談はさておき、名前だけは聞いたことがあるわね。何というか、あれよね? 竜と婚約したものの証。けれど、そんなことはあり得ないでしょ。……ことの真相はよけておくにしても、竜なんて、神話の時代に滅んだって話じゃない?」
そう発言する迷夢に対し、ベリアルは真摯な眼差しを送り続けた。
「――。まさか、それがデュレにあっただなんて世迷い言を言うつもりじゃないでしょうねぇえ? 幾らデュレが闇の使い手、ナンバーワンでかなりの魔力を駆使できるっていっても、女神の翼の刻印を持ち、それが故に潜在能力が大きいだなんて、あたしだって、感じたことはいのよ。だって、あれは……」
迷夢は言葉を呑み込み、珍しく動揺を隠せない様子だった。
「ええ、あれには相当な危険な要素があります。そもそも、竜と婚約させようという発想は現代においてはほぼ失われているといっても間違いないでしょう。しかし、ただ一つだけ、その思想を持ち続けたものがあったとしたら……」
ベリアルは敢えて解答を出さずに迷夢に答えさせようとした。ベリアルが迷夢に対しそんなことをするなど、尊大な賭けで、迷夢は答えてくれないかもしれないが。
「……ドラゴンズティース……」迷夢は呟いた。
迷夢とベリアルは互いに目を合わせて頷きあった。
「そうか、このあたしの目を欺いて本当に存在しているなんて、なかなかやるじゃない。しかも、竜との婚約、女神の翼を実現していたなんて。最高じゃない?」
「そうですね。しかし、ドラゴンズティースは存在してい『た』ですね。今はもう、存在していた痕跡も残さずに本当に何もかもが失われています」
「――つまり、それがキミの見てきたデュレの過去ってワケね。訊かせてちょうだい」
迷夢はクスリと微笑んで、目の前の椅子に腰掛けた。
『キミには全てを知る権利があるの。あれ? 違うかな? あー。義務があるの。ここまで来ちゃったんだから。デュレの封じた思い出を探り当てちゃったんだから、キチンと責任を取ってあげてよね?』
ベリアルの前から姿を消した金髪碧眼の少女の声だけが脳裏に響いた。そして、ベリアルの目前に広がるのは天を突くかのようにそびえる峰、ドラゴンズティースその物だった。この山奥で何が行われてきたのだろうか。ベリアルは足場の悪いごつごつとした岩だらけの道を答えを探すために歩いた。デュレは何を拒み、金髪碧眼の少女はベリアルに何を見せようとしているのか――。
「待て、お前は誰の許しを得て、ここに立ち入った」
突然の背後からの声に、背筋が凍りついてしまいそうなほどにベリアルは驚いた。そして、振り向く。そこにいたのはヒト? エルフ? 竜の面をかぶった男の素顔は知れなかったが、少なくともその視線はベリアルを突き抜けた向こう側を凝視していた。そして、ベリアルは再度、振り向く。すると、そこには一人のダークエルフが立っていた。
「わたしは闇の翼、貴様ごときに指図される筋合いはない」
闇の翼と名乗ったエルフは面の男をどかせると、ズンズンと奥へ行く。と、ベリアルは気が付いた。ダークエルフが近くにいる時は気が付かなかったが、エルフの足下にはすがるようにして幼い姉妹がいた。
「――お待ちしておりました」どこからともなくうやうやしい声がする。
「うむ。準備は出来ているな?」
「はい、準備は出来てございます」
子供を連れた男はドラゴンズティースの教主か何かなのだろうか。周囲を取り巻く者たちとは明らかに別格の風格を備え、全てに勝るような意志に下に行動しているかのようだ。ベリアルはその男の背中を追う。その男の風貌は滲み出る自信という名の風格以外には特に目立ったことはないようだった。すべからく、男を観察した後で、ベリアルは視線を少女たちに向けた。この二人のうちどちらかがデュレなのだろう。
「よく、訪れた。闇の翼よ。そなたの心は決まったのだな?」
「ええ、その通りにございます、竜の巫女さま」
(竜の巫女さま――?)
謎めいた呼び名にベリアルは顔を上げた。目線の先にはベリアルは見慣れない装束を身にまとった老婆が佇んでいた。“闇の翼”の言葉遣いからするに“竜の巫女”の立場はそれなりに高い位置にあるのだろうと推測できた。
「そうか、ならば、そなたの娘たちを我がドラゴンズティースの前に」
(ドラゴンズティースの前に……)
その言葉がベリアルの口をついた。竜の牙。神話の時代以前に滅んだとされる竜を信仰するという宗教だとはどこかで仕入れた覚えがあるのだが、それの存在はあやふやであくまで存在するらしいという憶測の域を出ないものだった。
(……ドラゴンズティース。竜の巫女さま……)
様々な考えがベリアルの脳裏をよぎっていく。リテールの宗教で最も根強いのはリテール協会だ。そこから枝分かれしたトリリアン、リテールの神々の神話、自然崇拝、精霊信仰へとつながっていく。神々の時代の前にあったとされる竜の時代の竜を信仰する宗教など皆無であるし、一般に竜は馴染みが薄い。さらに、リテールの住人は竜に対してあまりよイメージは抱いていない。
(それが何故、今更、こんなところで……)
「覚悟は良いな?」
重苦しい空気の中、巫女と呼ばれた女のしわがれた声が当たりに殷々と響く。返事を求められた少女たちは脅え、巫女の問い掛けに答えることは叶わなかった。
「――まあ、良い。こちらに来なさい」
巫女は姉妹を促して、さらにドラゴンズティースの奥へと足を向けた。無論、ベリアルもそちらに足を向けたのだが……。
「――? 見られている……?」
ベリアルは何かおぞましげな視線を感じ、つと振り向いたが、その視線の先に何かを見つけることは出来なかった。気のせいなのだろうか。今までにない初めてのパターンの精神シンクロに神経質になっているのだろうか。
と、一行は歩みを止めた。行き止まりだ。
風景は一向に変わる気配を見せず、ドラゴンズティースと呼ばれた山岳地帯そのままにどこまでも続く岩場ばかり。ヒトが長居できるような建物はなく、そもそも、そのようなもの建築できるスペースも一切なかった。
「――扉を開けよ!」
巫女が自分の前に壁のようにそそり立つ絶壁に手をかざすとズズズと重い音を立てて隠し扉が開く。そこは奥へとつながる薄暗い洞穴を利用した通路のようだった。その通路は緩やかな下り坂になっており、闇の深みに導かれるような息苦しい感覚を抱かせた。
「……竜の巫女さま。我が娘たちは竜の力を得られるのでしょうか?」
「判らぬ。我が教団の短からぬ歴史の中でも竜に見初められ、力を授かったものはホンの一握りに過ぎぬ。竜の力を得たにしても、強力過ぎる力に翻弄され制御できぬものや、心を壊すものが後を絶たぬでのぉ」
「では、わたしの娘たちは女神の翼は得られぬと……?」
「そこまでは言っておらぬ。他ならぬ、闇の翼の娘たちであるから、翼を得るだけの素養は十分にあると思っておるぞ」
巫女は乾いた笑い声をあげた。
「これより、儀式を始める」
『ねぇ、キミはどう思う? キミはデュレを信じてあげられる? これから先、何があったも、何を見ても、何を見なくても、デュレを信じてあげられる? ……信じて。キミはデュレを信じて。ここにいるキミだけはデュレを見捨てないで……』
そこから、記憶が飛んでいるようだった。見なければいい。見なければ良かった。デュレがベリアルを拒み、全てを記憶の奥に封じ込めたのにはあまりに壮絶な理由があった。けれど、同時にデュレは助けを求めていたのに違いない。それが金髪碧眼の少女の姿をとってベリアルの前に現れ水先案内人を買って出たのだろう。
『見捨てないで』
初めて会ったばかりのデュレからは想像もしていなかった言葉がベリアルの心を支配していた。見捨てないで。その言葉が端的に全てを表している。そう、逃げたい。許されるのならば今すぐにでも、この場を去り、二度と戻りたくはない。
「……まさか、……こんな……ことって……」
ベリアルは両手で口を押さえ、うしろによろけた。それは見てはいけなかったのだ。決して、デュレの記憶の淵から蘇らせてはいけなかったのだ。
『それでも、信じてあげて……』
その声だけがベリアルの脳裏にこだましていた。
*
エスメラルダはテレネンセス、エスメラルダ期成同盟司令部。そこには盟主・アズロ・ジュニアを筆頭に、ウィズ、サム、事実上の参謀として迷夢が首を寄せ合っていた。機は熟した。自らが望む全てをなしえるには今、この時をおいて他にはない。この時期を逸しては何もかもが水泡に帰す。
「でさ」重苦しい空気の中で、迷夢がずば抜けて明るい声で言った。「アズロ・ジュニアくん。あっちの方の段取りはうまくいってるのかしら? こっちが順調には進んだとしてもキミのところの準備がうまくいってなかったら、な〜にもならないわよ?」
ふざけた口調で言っているものの、目は真面目だ。ここで計画通りにはあまり進んでいないと言おうものなら、笑顔で鉄拳を喰らわせてくれるだろう。
「そうですね。……迷夢さんの杞憂も最もですが、何とかなりそうです。既にアリエスを立ち、順調に進めば、明後日にはアイネスタ入りを果たします」
アズロは机上で手を組み、自信たっぷりに言った。
「……予定通りに行けば……ね。……アイネスタ教会の司祭さまはばっちり?」
「そちらはテレネンセス大聖堂から手配し、今はすっかりアイネスタ教会の司祭さまです。万一、トリリアンの手の者が紛れ込んでいたとしても、ある程度なら対処可能です。それにこちらには有能な魔法使いが複数いますからね? しかし、問題点はある……」
アズロは敢えて自らその問題点を言わずに、迷夢の瞳をじぃっと見詰めた。
「……ただの司祭に戴冠式をさせたって意味がないのよ。エスメラルダ王家の正統性を照明できるだけの証拠と教皇にその場にいてもらわなければ、エスメラルダが国として対外的に認められることはあり得ない……。じゃあ、キミはどうするの? アズロ・ジュニア」
「そうですね……」アズロはそっと目を閉じ、そして、ゆっくりと開いた。
そもそも、迷夢には参段があるのだ。何をどう進めていくかハッキリとは口出しせずに、アズロに言わせる。実際はどうあれ、アズロが全権を動かしているように見える。
「――わたしなら、まず、あなたの目を欺くでしょう」
「あらっ! なかなか面白いことを言ってくれるじゃない?」
「それは軽い冗談ですが、わたしなら、迷夢さん、あなたを利用します」アズロの煌めく瞳の向こう側で何を考えているのかは手に取るように迷夢には伝わった。「こんなに凄い魔法使いが目の前にいるのを放っておく手はない。そうでしょう? 迷夢さん」
「確かにそうねぇ――」
迷夢は少しだけ上機嫌そうにアズロに微笑みかける。
「空間飛翔魔法を使って、教皇をアイネスタまで移動させる。出来ることなら、王子もです。それが最も危険が少なくかつ合理的だと思いますが、いかがですか?」
探るようにアズロは言う。
「教皇はそれでもいいわよ。年だし。けれど、王子については認めない。判るでしょ。これから国を背負って立つ人間に楽なことを覚えさせたら、あとで苦労するわよ? あらゆることは自分の力で手に入れてこそ価値があるの。過剰に手伝ってもらって手に入れたものになんて、何の価値もないわ。それが例え、多くの人の生活のかかったことだとしてもね。ま、どっちかって言うと、そうだからこそ、苦労して欲しいのよねぇ、あの子には」
「はぁ……、『あの子』……ですか?」
「そうあの子よ。だってまだまだ小童のスーパーキューティーボーイじゃない♪ ウィズと比べてもガキだし、サムと比べちゃったら、もう、どうしようかってほどでしょう?」
迷夢はアッケラカンとした様子で、軽く言いたい放題を言ってのける。
「なぁ、てめぇよぉ、仮にもこれから一国の王に言う言葉じゃぁ、ねぇよなぁ、それ?」
「そおかしら。あたしはあくまで客観的事実を述べたまでよ。ウソ偽り、誇張、インチキ、後ろめたいことなんて一つも言っていない」
迷夢は非常にステキな微笑みを浮かべていたが、胡散臭いことこの上ない。
「まぁ、言ってねぇよな」
サムは腕を頭のうしろに回しながら、面倒くさそうに言った。
「そ」迷夢は満足そうに微笑む。「さてと。じゃあ、ぼちぼち、キミたちにもしっかりと働いてもらおうかしら? ……これだけ、色々なことをやってるんだから、幾ら危うい求心力の上に成り立っているトリリアンだって、感付くでしょう? アルケミスタの教会をあいつらに押さえられたらあたしたちの負けよ」
かつて、エスメラルダ王国の王都があったその町には王家にまつわるものが多数残っているのだ。その歴史ある街で国の再出発をはかることに大きな意味がある。と考えていくと、エスメラルダという国もかなり不運だったといえることに思い当たる。国が出来、やがて、勢力を拡大したリテール協会に追いつめられ、国としての存在価値を失い、最終的には協会とトリリアンの抗争に巻き込まれる形で滅亡した。
「……エスメラルダ……か」上の空のようにサムが漏らした。
「どうかしたの、サム?」
「うん? いや、別にどうもしねぇさ。ただ、何もかも遠くなったなってよ。フとそう思った訳よ。まぁ、詰まる所、何で俺がここにいるのかなぁ〜ってさ」
「う〜ん、キミの場合はここに居場所を作るためでしょ、きっと。それに……何かをなすのに理由なんて必要なのかしら? それにそんなことはあとで考えればいいのよ。今は、目先のことをどうこなすかが先。あれこれ悩んだところで、時間の無駄」
迷夢はサムの顔を下から覗き込んで、意地悪そうな笑みを浮かべる。
「……ところで」アズロが口を開く。「わたしたちもそろそろ行動を起こさなければなりませんね。わたしたちの周辺は既に行動に移させましたから、残るはわたしたち」
アズロは執務机の前に居並ぶ三人の目を一人一人ゆっくりと見詰めながら発言した。
「トリリアンの目はしっかりと欺けるかしら?」迷夢はクスリとした。
「欺く必要なんてないでしょう、迷夢さん。ヘクトラはあざとい男だ。わたしたちが何をしようとしているか知っているはずです。……特にこの間のことで確信に変わったのではないでしょうか? 期成同盟がトリリアンに正面切って仇をなすということは……」
「トリリアンを潰しにかかり、その事実を利用してエスメラルダを再び、歴史の表舞台に立たせようとしていることを確信したということですよね?」
ウィズはアズロに向かって大きく一歩踏み出し、自信に満ちた態度で言った。
「……宗教が民衆を治める時代が終わるってことさ――」
サムは遠い昔を思い出すかのような静かな、どこかに憂いを含んだ表情をしていた。
*
「あ、いつつつ……」
雨が降ると頭痛がした。いつの頃からか記憶はないが、湿度の高い日には頭がズキンズキンと頭が痛む。まるで、古傷が痛むかのように。そして、そのような時には必ず“何か”を朧げな夢の向こうに垣間見る。二度と思い出したくもない記憶の深淵から蘇ってくる悪い夢のように。しかも、それは日を追う毎、回数を重ねる毎に鮮明になってくるのだ。
「わ、わたしは一体……」
記憶がないのに記憶がある。そんな奇妙な感覚を持つようになってどれだけ過ぎただろう。自分自身が全く身に覚えの無いことが不意に脳裏をよぎることが多々あるようになった。所謂、デジャビュにしては鮮明で、妄想にしても異様なほどのリアリティを抱えている。何が自分を追い込もうとしているのだろうか。
「黒い翼の天使……」
その姿はどこかで見たことがあった。誰か別の人の目を通して見ていたかのような感覚が残っていたが、確かに自分以外の黒い翼の天使を見ていた。いや、そもそも、召喚されて以来、白、黒の如何に関わらず、天使などにお目にかかったことはない。そんな奇妙な記憶の他にも記憶があった。自分以外の誰かが経験したはずの、けれども、自分がそれを見、それを体感したというおかしな記憶が……。
「――。やめて……。やめてっ! わたしは――」
「わたしは――お前だ。わたしのしたことはお前のしたこと。覚えておけ」
「やめて。お願い」
自らの意志に反して腕が動く。自らの意志に反して唇が破滅の呪文を唱える。全く知らない未知の言葉が自らの唇からよどみなくあふれるのだ。
「……お前はわたしとともにある」
何者かが悪辣な表情を浮かべて、嘲笑ったような空気の流れを感じた。そう、笑っているのだ。眼下に広がる小さな街並みに向けて、差し向けられた己が右手。“ゆーりすか”不意に。何の切っ掛けがあった訳でもないのにその言葉が脳裏に浮かんだ。
「お前が滅ぼした街の名だ……。お前がその手でそこにあった全てを打ち砕いた」
「知らないっ! わたしは何も知らないっ! 信じて、わたしを信じてくださいっ!」
黒き翼のその声は狭い地下牢に虚しく響いた。
文:篠原くれん 挿絵・タイトルイラスト:晴嵐改
