09. dragon's teeth(竜の牙)
その日以来、ジェットの地下牢に立ち寄ることはクローバーの日課になっていた。同情なのか、せめてもの罪滅ぼしのつもりなのか立ち寄るクローバーにすらよく判らない。ただ、客観的に考えれば、それは自己満足に過ぎないことはクローバー自身がよく心得ていた。それでもなお、クローバーはジェットのもとに足を向けた。
「黒き翼の天使……。異界から召喚された最後の天使……」
出会いがこのようでなかったら、クローバーはジェットに激しく魅かれていたかもしれない。そう思うほどに、ジェットは美しく、可憐に見えた。
「ジェット……。キミは、何故、ここにいるんだい……」
フとクローバーの唇から言葉が漏れた。意識した訳ではない。ホンの無意識のうちに。天使のいなくなった世界にどうしてジェットはいるのだろう。無論、そうなってしまった理由は知っている。けれど、何故、ジェットがこの世界に召喚されたのだろう。深い意図は全くない素朴な疑問だった。
「わたしは……どうして、ここにいる……の?」
ジェットに答えられるはずもない。ジェットにしても気が付いた時にはこの世界に立っていたのだ。ジェット自身がこの世界を訪れたいと願ったのではなく、強制的にこの世界のもっともいやな部分に召喚された理由を知るはずはない。
「判りません――。ただ、誰かに呼ばれたようにな気がして――」
気が付いた時にはこちら側の世界に立っていたのだろう。クローバーの紐解いた多くの古文書の大半にそのような天使の証言が載せられていた。
「――そうですね。――そうでなければ――」
好き好んで地下牢に幽閉されるような選択はしないだろう。
と、何かから逃れるかのようにジェットが後ずさったのをクローバーは感じた。その行動は自分の避けようとしたのではなく、他の何かから逃れようとしたらしいが、クローバーに感じられる気配は何一つなかった。
「……君を傷つけようとするものはいないよ――」
(さあ、わたしに身を任せて……)
「――やめて――来ないで」呟くような声色。
ジェットの瞳はクローバーを見ることはなく、あるはずのない虚空の何かを見ているようだった。その瞳は襲ってくる恐怖に立ち向かうかのように微かに震え、潤んでいるようだった。突然、ジェットの身に何が起きたのかクローバーには理解不能だった。
「誰、なの……? わたしに話しかけるのは誰なのっ!」
「ジェ……ット?」
取り乱したジェットを前にクローバーはただ立ち尽くすしかなかった。
*
そして、デュレの心の風景を垣間見てしまったベリアルもまた立ち尽くしていた。荒涼としたイメージ。何かを必死に覆い隠そうとしているようだが、雨の降る街並みから感じられるのは淋しさと孤独でいっぱいのイメージだった。まるで、誰かに、手を差し伸べてくれる誰かが訪れてくれることをずっと待ち続けていたかのように。
耳をつんざくような悲鳴の真相は何なのだろうか。
唯一提示された手がかりなのだから、ベリアルは行かない訳にはいかなかった。降りしきる雨に行動を阻まれ、暗闇に拒絶される。はっきりと見えるのは薄く開いたドアから漏れる一筋の光だけ。呼んでいる。それだけがベリアルを待ちわびているかのように。
ベリアルは駆けた。呼ばれるがままに。
ただそれは本当にベリアルを呼んでいたのだろうか。その悲鳴は本当は全てを遠ざけるための手段だったとしたら。
“ここはお前の来るところではない”
“お前はここにいてはならない”
拒絶。しかし、ベリアルはその中に微かな声を聞いた。
“……助けて――。お願い……わたしをここから――”
忍び寄る魔の手にデュレはどう耐えてきたのだろうか。不安がよぎる。そして、その不安は明かりに近づくほど大きくなっていく。払拭されない陰鬱な思い。恐らく、ベリアルの行く先に待っているのは“悪夢”にほかならない。そんな気がしてならないのだ。
そして、ベリアルは降りしきる雨の中、戸口に立ち尽くした。
それは決して見てはならない“絶望”だったのかもしれない。幾多の悪夢と絶望をくぐり抜けてきたベリアルにさえ、それは信じられず、忘れ得ぬ光景だった。うつぶせに倒れたエルフの男。恐怖に戦き壁際にぴったりと張り付くエルフの女。そして、血染めの短剣を握りしめた少女が一人。
「……。そこに……いるのは……だぁれ……?」
全く生気の感じられないその声色にベリアルは戦慄を感じた。ここで何が起きたのか。いや、その問い自体がナンセンスだ。ここでは何も起こっていない。ここはデュレの無意識を介したビジュアルがあるだけなのだ。
「――答えがないのは名無しさんだから……? それともわたしに答える名前はないってことかしら?」かなり攻撃的だ。
「――それは……」
どういう事態なのかベリアルの理解を越えていた。こんな暗闇を見たことはない。果てしなく続く心の闇。確かに風景こそある程度は見えるものの。、其処はまるでスポットライトを浴びた小さな舞台。舞台の袖から走り出たベリアルと舞台中央をさめざめと照らすスポットライト。観客席のない演舞場で一際の淋しさと孤独感を感じてベリアルはそこにいた。そう、ベリアルがここに辿り着いてから感じていたのはデュレの孤独感なのかもしれない。心臓が凍りついてしまいそうなほどに冷たく閉ざされた闇は凍りついてしまった心をさしているのかもしれない。
「それは――あなたが……呼んだから……」
「……わたしはお前なんて呼んでない……。出て行け……」
まだあどけなさの残る女の子の横顔が歪んで見えた。けれど、ベリアルには見覚えがあった。先程対面したばかりのエルフの女。ダークエルフ。成長した少女の顔にはこの女の子の面影がしっかりと残っているのだ。
「出て行けっ! ここはお前のいるところじゃない。わたしは……、わたしは何も知らない。わたしは何もしていない。だから、消えろ。お前なんて消えてしまえ。お前になんか何も見せない。何も教えてやらない」
「わたしは……何も……」ベリアルは女の子の迫力におされ口ごもった。
「うるさい。お前はわたしを惑わすためにいるんだ、だから――」
くらっと視界が激しく揺れ動き、めまいに襲われた瞬間、ベリアルは再び、身も知らぬ場所に投げ出されていた。まさに“初めての体験”精神シンクロを試みて、急流下りをしているような感覚にあったことはない。
そして、しんとした静寂に包まれたここはどこなのだろう。
「……ねぇ、キミは知りたいの?」
地面に伏したベリアルの背中の上から誰かの声が聞こえた。幼い声色。年の頃はさっき出会ったデュレと大差ないと思われた。しかし、その声色はデュレの声色とは明らかに違った。精神シンクロでは世の中のありとあらゆる事象を使ってその内面を表現するといっても過言ではないが、それでも年端の行かない女の子が自分の心を代弁する役柄として登場することはとても珍しい。
「ねぇ、キミは知りたいんでしょ?」
その女の子の声は執拗にベリアルに迫ってきた。絶えず声は明るく、否定されることなど夢にも思っていない様子だった。幼いデュレとは裏腹にこっちの女の子はベリアルに何かをどうしても伝えなければならないという使命感に燃えているかのようだった。
「……あたしが知ってる……。だから、あたしが見せてあげる……」
幾度目かの問い掛けの時、ベリアルはようやく地面から起き上がって、声の主を確認した。その女の子はベリアルには全く面識がなかった。さっき、ちらりと見たデュレの両親(?)のようでもなければ、どう見てもデュレ本人でありはしない。金色の髪、白い肌、青い瞳。何一つ、ダークエルフの特徴を備えていないその少女は何者なのだろう。
と考えているうちに、少女はトタタと駆け出した。
そして、ベリアルが動けないでいることを悟ると立ち止まり、振り返った。
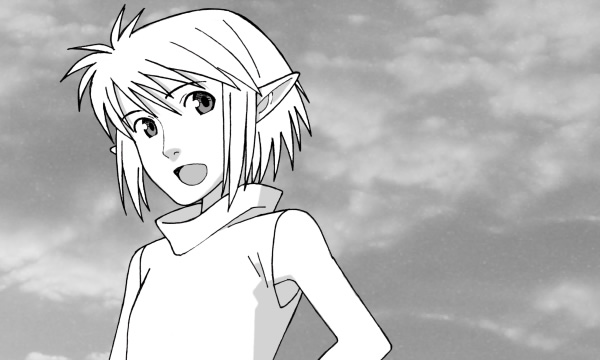
「……付いて来ないの? と言うか、付いて来なさい。キミは知りたいんでしょ?」
ベリアルは呆気に取られて頷いた。そう、知りたいのだ。この僅か数瞬の出来事に何が凝集されているのかを余すところなく知りたいのだ。そうしたら、何故、デュレがそこはかとない絶望感、ないしは淋しさを抱いているのか理解できるに違いない。
「そう。じゃあ、あたしが水先案内人になってあげる。デュレに任せたら、先に進めないから。だって、キミの一番知りたいことはデュレが一番触れられたくないところだから」
金髪碧眼の女の子は端的に全てを言い、再び、駆け出した。
ベリアルは追う。金髪碧眼の女の子が何もか判らなく、仮に彼女がベリアルを体よく追っ払うために現れたのだとしても示された手がかりなのには変わりない。凍てつく眼差しと、血塗れの短剣を持った少女は何なのか。それの尋常ならざる圧倒的な拒絶。ベリアルを排すというよりはむしろ、その記憶を自己から永久に排斥したいかのように。
「……あなたは……」ベリアルは問う。
「さあ? あたしは誰でしょう?」女の子は面白おかしそうにケラケラと笑う。
刹那、周りの景色は流れるまでもなく、一気に入れ替わった。
雨に濡れた街は唐突に空白地帯へ。しかも、そこはただの空白地帯ではないようだった。知っているかもしれない。観光に来るような場所でもなく、ヒトが住むような場所でもない。よほどの物好きが思い出したかのように時折、訪れるようなそんな場所。
それでも遥かな昔、この場所もにぎわったのだという。
そこはドラゴンズティースと呼ばれる山岳地帯だった。リテール北部の連峰で数々の命知らずの冒険家の命を食い荒らしたとも言われる場所だった。名の由来は竜の牙を連想させる連峰とかつてこの場が良質な“竜の牙”の産地だったことから来ているようだった。
「……キミはこの場所を知ってる……?」
「――ドラゴンズティース」ベリアルは震える声で振り絞るように言った。
「そう、ご明察。あたしはキミがこの場所を知らない方に賭けてたんだけどな。――へへっ、この賭け、ひとまずはデュレの勝ち。けど、ここはまだ、何でもないの。真相はむしろ、ここから。キミは最後までちゃあんと付いて来られるのかしら?」
女の子の意味深な言葉にベリアルは戸惑いを感じた。普通は精神シンクロを仕掛けた方がある程度のイニシアティブをとれるはずなのだが、今度はほぼ皆無。どう楽観的に考えてみても、目の前の女の子が自在に自分自身を誘導しているように感じられた。逆に考えれば、それだけデュレの我が強いと言え、ちょっとばかり厄介だ。
それから、女の子は軽快にタンと地面を蹴ると、再び走り出した。
「待って、ここには何があるの?」
「――さぁ?」女の子は横目でベリアルを見ると肩越しにクスリとした。
知ってるのだ。知っているが、直接話すつもりはさらさらないようだった。では、自力で調べるか、目の前を軽快に走る女の子から聞き出す他ない。
「じゃあさ、サラマンダーズバックは知ってるよね?」
女の子は不意に話しかけ、ベリアルをチラリと見た。
「え? ええ」意表を突かれ、ベリアルはしどろもどろに答える。
「じゃあ、それがヒント」女の子は軽快に駆け抜けていく。
「サラマンダーズバックとドラゴンズティース。つながりはどちらも竜ということ……」
しかし、両者は地理的には南北に大きく離れており、ほぼ無関係だ。
「じゃじゃ〜ん。第二ヒント。サラマンダーズバックには何があるかしら?」
「伝説では竜の心臓があると……」
「そうっ! じゃあ、ドラゴンズティースには?」
少しからかうような口調がカンに障るが、ベリアルを的確に答えに導こうとしているのがハッキリと判る。だから、ベリアルは出来るだけ平静さを装った。
「竜の牙……?」
「YES! でも、それだけじゃあないよね?」
女の子はピタリと足を止めるとベリアルに振り向いて不敵な笑みを浮かべた。何となく、その微笑みにベリアルはかちんと来たものの、その指摘も外れてはいない。ここは山々の形状からドラゴンズティースという名が付いていたり、竜の牙がここ眠っているからそう呼ばれているのではないと何かで読んだような気がする。ほとんどの場合はより商品価値のある竜の牙に目がいってしまうが、それ以外のものも多数埋もれているのだという。
一説によれば、このドラゴンズティースにも火竜ではない何者かの心臓が埋もれているとも聞くし、そもそも、竜さえも生きながらに封じられているという伝承も数多い。それでも、竜が蘇り、ヒトに仇なすというのならさほど恐れることはないかもしれない。現世の超一流魔法使いを集めれば、最悪の事態くらいは免れるだろう。
「……ドラゴン……、竜の牙……」
ベリアルは自分の考えていることがあまりに恐ろしくなって、ゴクリと唾を呑み込んだ。ここにはかつて何かがあった。リテールに所謂リテール信仰があったように、ここにも。しかし、それは存在していたらしいというところまでにとどまっていた。
「……竜を信仰の対象とした秘教の地ですね……。竜の復活とその支配を望み、非人道的な儀式を繰り返したという……秘教・ドラゴンズティース……。ただ、それはあくまで伝説上のお話で実在したとは聞いたことがありませんよ?」
他にハッキリと言い切れることもなかったので、とりあえずベリアルは発言した。けれど、女の子から返ってきた答えは意外なものだった。
「そう。だけど、あったのよ。今から、それを見せてあげる。キミは知りたいって言ったんだから、最後まで見ていくのよ? 何を見ても目は逸らさない。キミは――ここを知らなければならないの。デュレを……助けてあげて。きっと、キミしかいない――」
存在すらも不明とされてきたドラゴンズティース。それが今、ベリアルの目の前にある。一人のダークエルフ・デュレの過去とドラゴンズティースと一体何の関係があるのか。恐らく、それは決して開くことを許されることのなかった禁断の扉だったのだろう。
「……デュレを“絶望”から救ってあげて……」
その一言を放つと、ベリアルを導いた女の子は消えていた。
*
ジェットとの一戦、対トリリアン前哨戦から一夜明けて、迷夢はデュレ宅に顔を覗かせていた。期成同盟だけに全てを負わせるのには難がある。やはり、魔法に通じた者たちとやり合うにはこちらも魔法に通じている必要がある。それは一朝一夕に身に付けた知識とも呼べない知識ではなく、全てを知り、魔法を使いこなすスキルを持ったものが必要だ。となれば、必然的にこちらに足が向いたと言う訳だ。
「で、天下無敵のキューティーガール・迷夢ちゃんが何の用かしら?」
デュレ宅を訪れると居候ともいえるセレスが迷夢に声をかけてきた。
「――珍しくあたしが来たからって、何で突っかかってくるのよ? 小猫ちゃん、その二。……。は〜、さては焼きもちを焼いてるな?」
「一体、何の焼きもちよっ!」セレスは思わず大声を出した。
「何のって……。さぁ、何のかしら? ま、そんなことよりさぁあ、デュレはいる?」
迷夢はセレスを押しのけるとさらに家の奥に分け入ろうとした。呑気にセレスと戯れている場合ではない。これから先、寸刻を惜しむような事態になっていくことは疑いようがない。トリリアンと期成同盟、どちらが先に己の目標への足がかりを作るかが焦点になってくるだろう。そのためにはデュレや、かつての戦友が必要なのだ。
「ねぇ、デュレってば?」
「デュレってば、まだ帰ってきてないんだけど……? あたし、キミに会ったあと、デュレと会ってさ、そのデュレはキミに会いに行くって言ってそのまま一晩、行方知れずなんだけど……、もしかして、迷夢が一枚かんでるんじゃないの?」
セレスは意地悪そうににんまりと微笑んで、迷夢の脇腹を肘でつんつんと突っついた。
「……キミ、そんなに死にたい?」迷夢も負けずに不穏な笑みを浮かべた。
「い? いや、この若さで死にたいワケないっしょ? イヤだなぁ、迷夢。本気にしないでよ」笑いながら左手をヒラヒラ。「ホンの戯れに決まってるじゃない……ね?」
「ま、いいけどさ。で、デュレは?」
「……」また、そこかい。と突っ込みたくなるところをこらえてセレスは言った。「え〜、宅のデュレちゃまはただいま、お出かけ中です。いつ帰宅するかは全く判りません」
「ふ〜ん?」迷夢は腕を組んで、訝しげな表情でセレスを見つめた。「丸一日帰ってこないなんて変ねぇ。ちょちょっとやってすぐ帰ってくるはずだったんだけど……。――! ねぇ、セレス、キミ、デュレを隠してるんじゃないの?」
迷夢は一歩踏み込んで、セレスの顔を下からのぞき込んだ。
「むあっ。何なのよ、キミはっ!」セレスはのけ反って迷霧をかわす。
と、そこにギギギと厳めしい音を立ててドアの開く音が聞こえた。扉が開くと敷居のところに疲れ切った様子のデュレの姿があった。しばらく、入口で立ち尽くしたあと、デュレはツカツカと足早に迷夢のもとに歩み寄った。
「話が違うじゃないですか、迷夢さんっ」
「あら〜、話なんてしたかしらぁ?」迷夢はつーっとデュレから視線をそらした。「それにキミの言う“違う”と言うのはベリアルが独断で進めたことだと思うのよねぇ、あたしは。だから、あたしは無関係。そこんところ、よろしくっ! ま、そんなのはどうでもいいからさ、あたしはデュレに用事があるのよ。ちょっと、顔貸して」
そう言うと迷夢はデュレの肩を抱いてズリズリと奥の方に引きずっていった。
「な、ちょっと、あたしを仲間外れにしないでよねっ」
置いてきぼりをくったセレスは慌てて、デュレと迷夢の後を追った。自分抜きでデュレと迷夢に秘密会議をされたらたまったものではない。二人で策略を巡らせて、気が付くとセレスはとんでもない役割の分担になっていたりするのだ。
「で、あたしたちの仕事は黒き翼の天使を解放すること」
「……黒き翼の天使を解放する?? ってキミじゃん? あたし、黒き翼の天使だなんて、迷夢しか知ら……」と言いかけて、セレスは思い直した「マリスとレイヴンしか知らない。そもそも、黒き翼の天使なんて珍しいんじゃないの? その昔、協会が擁していたという天使兵団でも白き翼の天使で百パーセントだったんでしょう?」
「だけど、いたのよ。トリリアンに」
「どうやって、そんなことまで調べ上げたんですか?」
デュレが問う。すると、迷夢は待ってましたとばかりに喋り出した。
「内部に協力者がいるの」
「向こうの連中にしてみたら、裏切り者ってことよね」
「う〜ん、そうかなぁ?」迷夢はわざとらしく声を上げて、ニヤリとした。「セレスのような見方も出来るけど、それじゃあ、かなり近視眼的と言わざるを得ないわね。もっと、時間的に視野を広げてみると見えなかったものが見えてくると思うのよね。裏切り者かそうでないかはトリリアンの全てを知ってからでも遅くないんじゃない?」
「――トリリアンの全てって何よ……?」セレスは居心地が悪そうに呟いた。
「じゃ、デュレ。ちょっとでいいから、セレスに説明してあげて」
迷夢はちょいちょいとデュレの肩を叩くと説明を促した。
「はい。トリリアンは独自に組織化するまでは“リテール協会アリクシア派”と言われていました。ですが、ナカデミアン公会議で異端認定され、協会から追放されました。その後、その教義内容から自らを“トリリアン”と名乗り、現在に至っています」
「デュレって協会の歴史にも詳しいのね?」
「当たり前です。魔法学園に籍を置いたものでこんな事も知らないなんて、セレスくらいですよ。――もう一度、高校生からやり直した方がいいかもしれないですね?」
デュレは嫌味たっぷりにセレスに言った。
「……あの、嫌味を言ってる場合じゃないと思うけど……?」
「言いたくもなります! 大体あなたは学校を出てから少しでも勉強をしてるんですかっ」
「いやぁ……」セレスは照れたように左手で後頭部を掻いた。「ノーコメントで」
「何、寝ぼけたことを言ってるんですか!」
「寝ぼけてない、あたし、いつでも本気だから」
「じゃ、トリリアンが何故、“トリリアン”なのか説明して見せてください」
「げっ」セレスは蛙を潰したような声を上げた。
「まさか……答えられないワケではないですよね?」デュレはズイとセレスに迫った。
「――セレスに答えを求めようってのが間違ってるんじゃないの?」
迷夢は横から口を挟むと、セレスの頭をポンポンと軽く平手で叩いた。それは迷夢の挑発とも取れたが、セレスにとっては妙に屈辱的だった。
「ど〜もすみませんね。ど〜せ、あたしには答えられませんよ〜だ。ふんっ」
「――リテール協会アリクシア派、教義がヒト、エルフ、精霊の三種協和から、後に自らをトリリアンの呼び習わすようになる。ただ、それだけのことです。……たったそれだけのことも知らない、覚えていないなんて、終わってますね、セレスさん」
デュレはここぞとばかりにセレスを追いつめた。
「うぐぐ、そんなこと言ったって、知らないものは知らないし、覚えていない……」
「まぁ、まぁ、デュレ。セレスを問い詰めるのはあとでゆっくりしてちょうだい。それより今はあのコをどうやってこちら側の世界に引き戻すかの方が重要なんだから。――そこで、皆さまのご協力を賜りたいのよ。あたし一人だとやっつけることは出来るんだけど、捕獲するのは難しくて……」
迷夢のあり得ない発言に一同は完全に呆気にとられすっかり黙り込んでしまった。
「ちょ、ちょっとキミたちはあたしが頼みごとしたらダメだって言うの?」
「い、いえ、そんなことはないんですけど……。少しだけ、意外だったかな……と」
「意外ね……。なら、キミの予想の範疇を越える意外なことはこれから先、もっと多くなるわよ? キミの狼狽える姿がたくさん見られるかと思うとワクワクしちゃうわ」
嬉々として迷夢は言う。他人の不幸は結局、蜜の味なのだ。
「……あの〜、そんなところで喜ばないでもらえるかしら……」
「あら? 喜怒哀楽ははっきりしないとストレスがたまるわよ?」
「ストレスなんてもう、たまり放題よっ」セレスは憤慨して怒鳴った。
「あ、そう。それはそれとして、デュレ。キミ、しばらく、ベリアルと行動を共にしないさい」迷夢はズビシとデュレを差した。「詳しいことはおいおい説明していくとして、この作戦の成否はキミの双肩にかかってるんだからよろしく頼むわよぉ」
「え? はい、あの、その。え?」
あまりに唐突な出来事にデュレは自分のおかれた状況を把握できなかった。
「うん、そう。帰ってきたばかりで悪いんだけど、アルケミスタに戻って。今すぐに。あたしの言う事を聞けないってなら、どんなことになっても知らないんだからねぇえ?」
不穏なこと極まりない笑顔で迷夢は言った。
*
今でもよく覚えている。扉の隙間から一条の光が差し込んできた日のことを。けれど、希望の光と信じたそれは絶望のまやかしだった。法衣を着て、優しそうな笑顔で差し出された手のひらに“救い”を感じたのはただの思い込みだったのだろうか。
その日を境にジェットの中に何かが生まれた。“それ”だけは意識できたが、“それ”が何なのかまでは認識できなかった。ただ、確実に“それ”が自分の中にあることまでしか判らない。そして、“それ”が恐怖であること以外は。
「ここは……。あなたは誰ですか?」
不意にジェットは尋ねた。誰かが見ている。いや、本当は誰も見ていないのかもしれない。けれど、感じる。どこかで、何者かがジェットを見つめている。
「――わたしを見ないで……」
(……わたしはあなたなんか見ていない……。わたしが見ているのはもっと遠く……)
答えはなかった。ただ、判るのは暗闇に埋没するかのように自分があることだけ。
コツコツコツ……。無機質な乾いた靴音が響いた。
「……あなたは……あなたは……誰ですか……?」
「わたし? わたしはクローバーだよ。君をここから助け出しに来ました」
とうとう言ってしまったその言葉はジェットにとって福音だったのだろうか。
文:篠原くれん 挿絵・タイトルイラスト:晴嵐改
